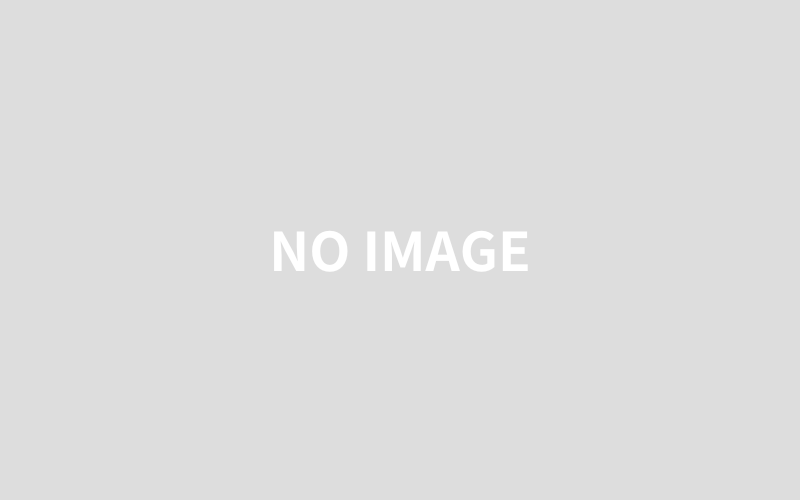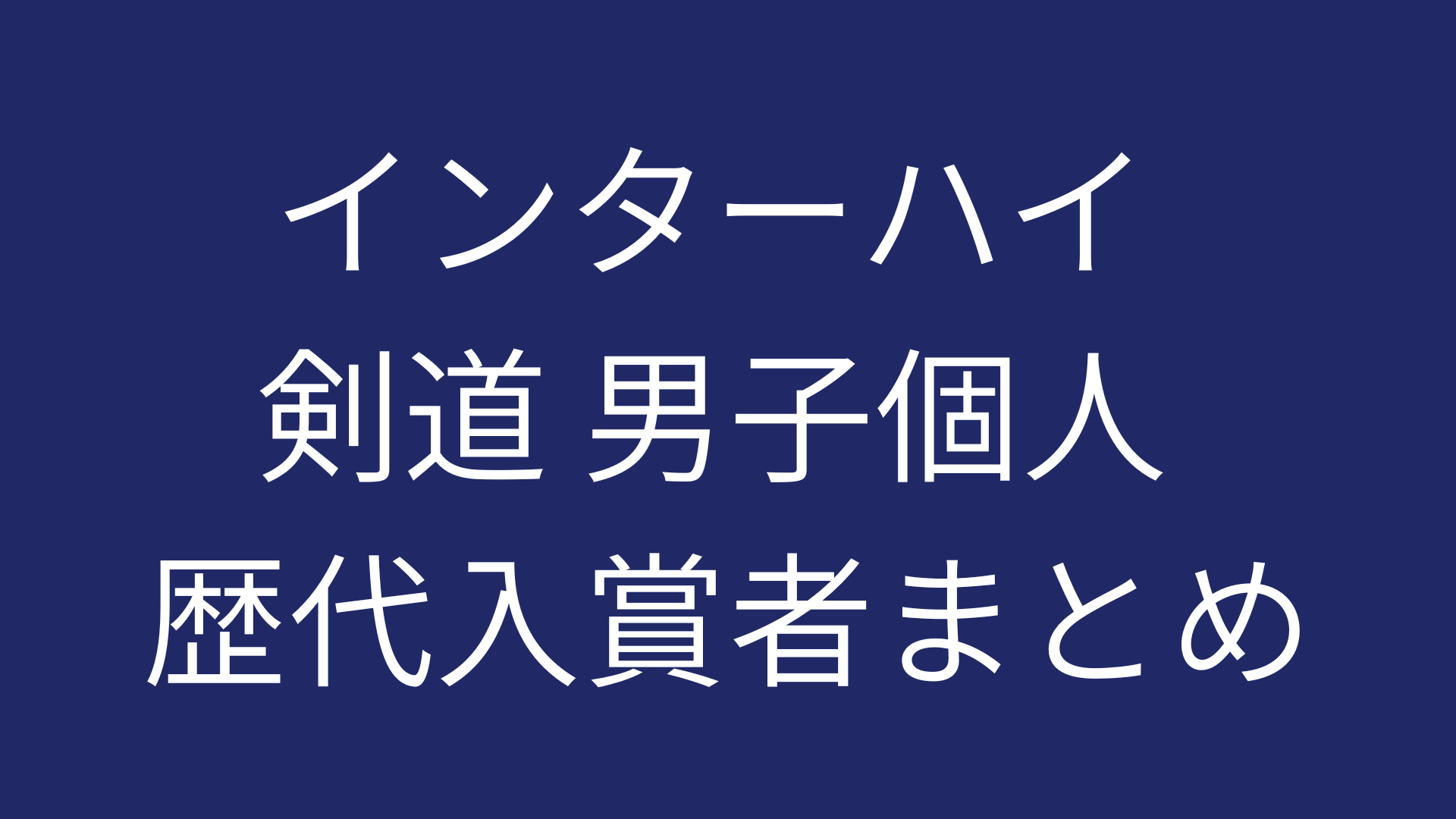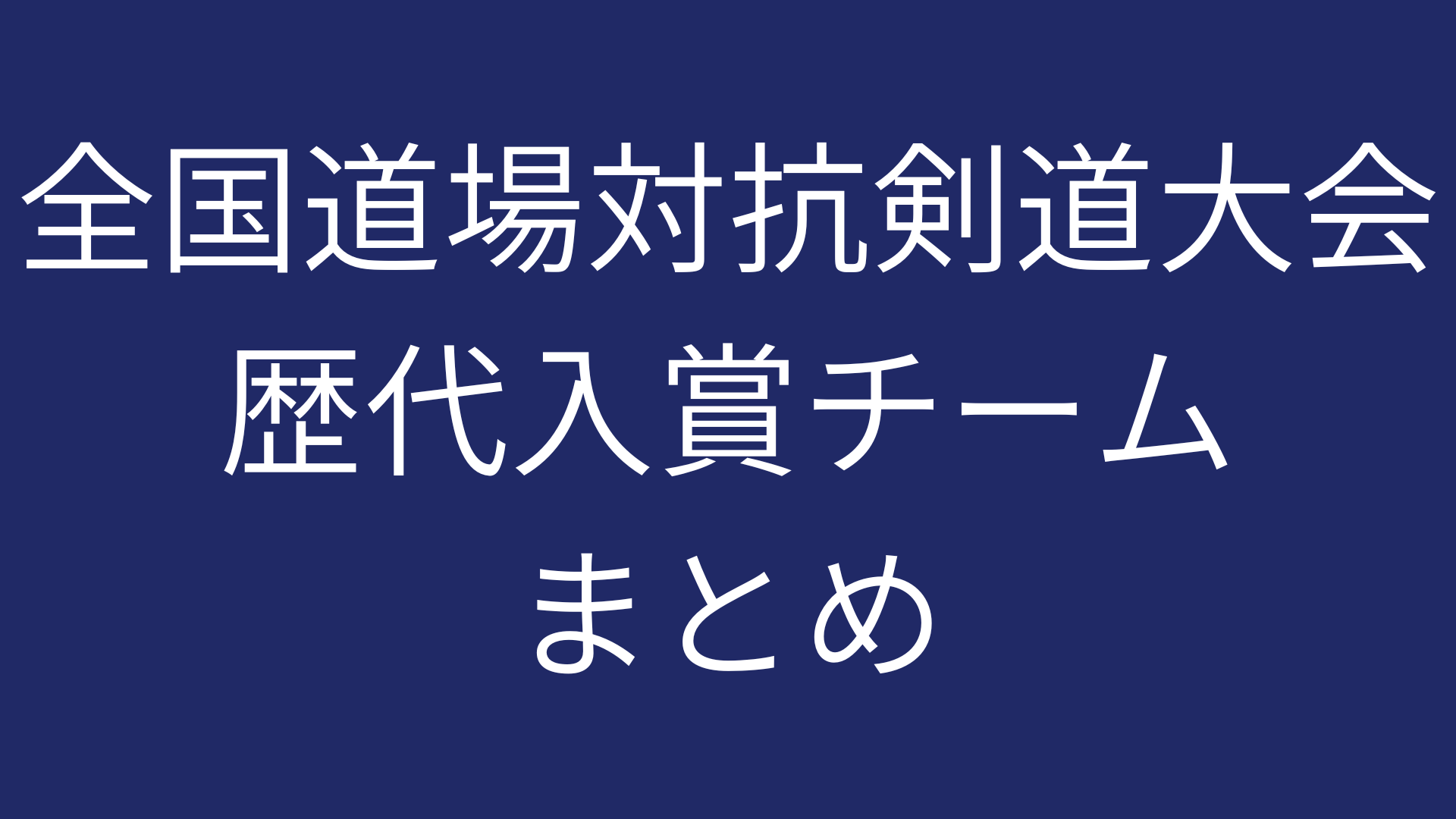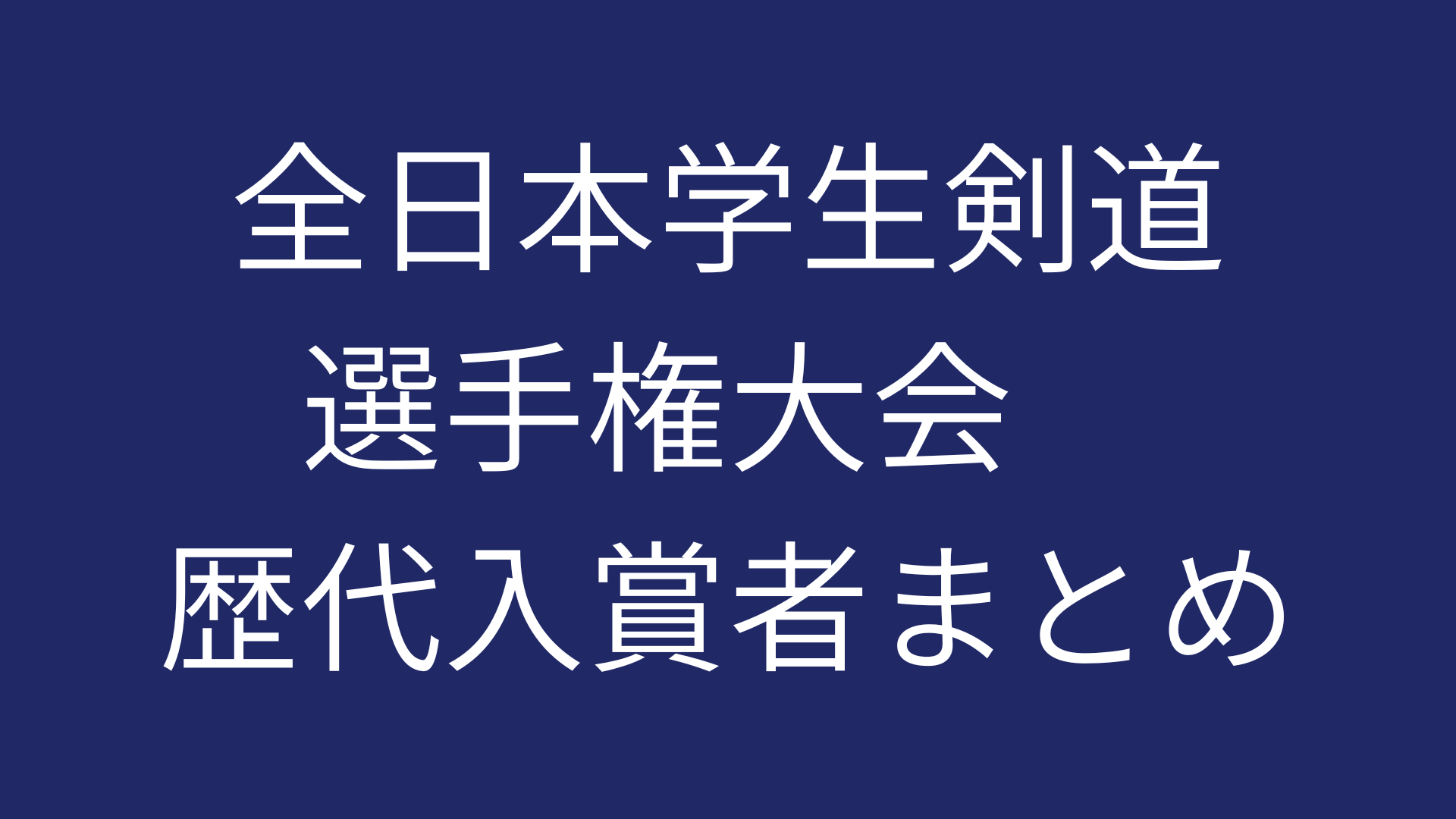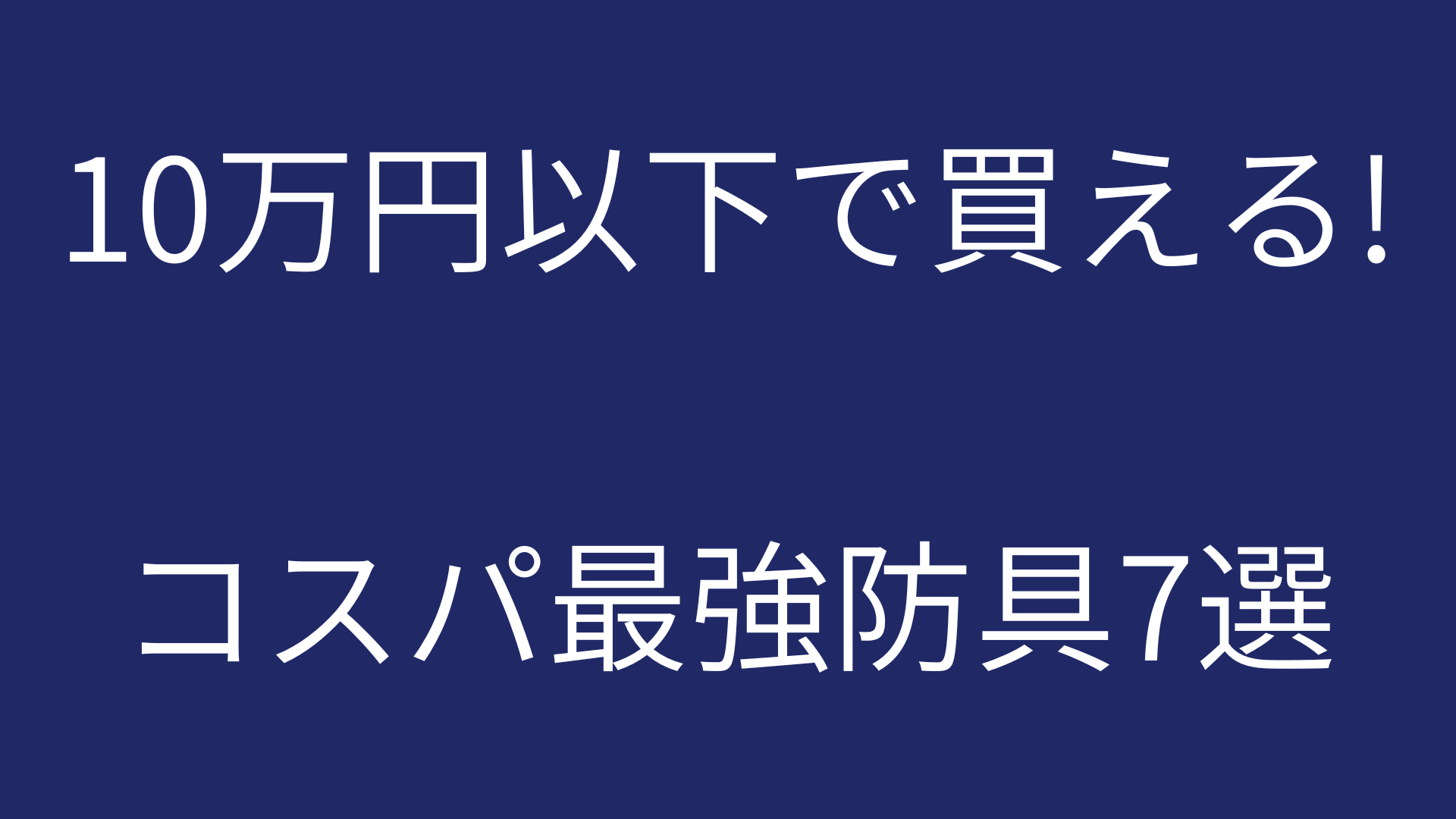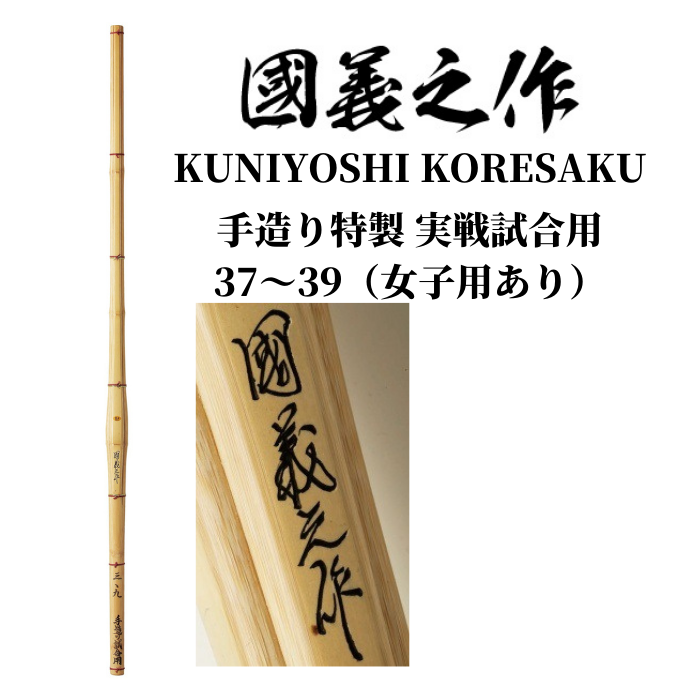剣道をされている方であれば、一度は稽古中に「竹刀の点検をしておきなさい」と指導者から声をかけられた経験があるのではないでしょうか。
しかし実際のところ、竹刀の正しい手入れ方法や破損した竹刀の安全な点検手順を、体系的に理解している剣士は意外と少ないものです。
「なんとなく磨いている」「ささくれを削っているだけ」という方も多いかもしれません。剣道をやっているお子様をもつ親御さんはどうしてよいか分からなくて困っているという話もよく聞きます。
本記事では、初心者から上級者まで知っておきたい竹刀の基本的なメンテナンス方法をわかりやすく解説します。
さらに、購入直後に行うべき竹刀の慣らし方や、長持ちさせるための保管・ケアのポイントまで、専門的な視点から丁寧に紹介します。
竹刀とは
 剣道において使用される竹刀(しない)とは、単なる練習用の道具ではありません。
剣道において使用される竹刀(しない)とは、単なる練習用の道具ではありません。
全日本剣道連盟では、「剣道は、竹刀による『心・気・力の一致』を目指し、自己を創造していく道である」と説いています。
さらに、「竹刀という剣は、相手に向ける剣であると同時に、自分に向けられた剣でもある。この修錬を通じて、竹刀と心身の一体化を図ることを指導の要点とする」と述べています。
つまり、竹刀とは心と技を磨くための象徴的な存在であり、剣道そのものの精神を表しています。
現代の剣士も竹刀を神聖なるものと捉え、竹刀を持てることに感謝し、取り扱わなければなりません。そのため竹刀を跨いだり足で蹴ったりするようなことはしてはいけません。
竹刀を点検する理由
竹刀を点検する理由は、破損した竹刀をそのまま使用して稽古をすることが大変危険だからです。
竹のささくれが相手の目に入る危険性もありますし、割れた竹が防具で覆われていない部分に刺さることもあります。それだけに留まらず、先革の緩みなどがあると、そこから竹が飛び出るという恐ろしい事態につながりかねません。
稽古中も小まめに竹刀を点検し異常がないか確認すること、稽古後にはしっかりと手入れを行うことは、剣道家の基本であり、また相手を傷つけないようにという敬意の表れでもあります。
関連記事 竹刀の点検と調整の仕方まとめ!https://bushizo.com/media/202007/4279/
竹刀の手入れ方法
 竹刀の点検中に破損が見つかれば、その竹刀はすぐに使用をやめ、代わりの竹刀を使いましょう。稽古後には竹刀の手入れを行ってください。ここでは竹刀のそれぞれの部位の点検方法、及びそれらの部位に破損がある場合の手入れ方法について紹介します。 ※手入れに必要な道具 竹刀削り、サンドペーパーがあれば十分です。また竹の割れを防ぎたい場合には、竹刀油などの油もあると効果的です。
竹刀の点検中に破損が見つかれば、その竹刀はすぐに使用をやめ、代わりの竹刀を使いましょう。稽古後には竹刀の手入れを行ってください。ここでは竹刀のそれぞれの部位の点検方法、及びそれらの部位に破損がある場合の手入れ方法について紹介します。 ※手入れに必要な道具 竹刀削り、サンドペーパーがあれば十分です。また竹の割れを防ぎたい場合には、竹刀油などの油もあると効果的です。
サンドペーパー型竹刀削り竹磨くん
竹刀削り匠
・竹
竹は、竹刀の中でも特に打突の衝撃を最も受ける部分です。
その中でも「物打(ものうち)」と呼ばれる箇所は、稽古で何度も打突が加わるため、ささくれや亀裂が生じやすくなります。
放置すると破片が相手に飛んだり、防具の隙間に刺さる危険があるため、稽古前後には必ず点検を行いましょう。
竹刀のささくれ・亀裂の確認と修理方法
次のポイントを重点的に確認します。
1,物打部分にささくれがないか
2,亀裂や割れが発生していないか
3,カーボン竹刀の場合は繊維が露出していないか
これらを日常的にチェックすることで、安全性を保ち、竹刀を長持ちさせることができます。
ささくれを見つけたときの対処法
小さなささくれの場合は、竹刀を分解せずに竹刀削りやサンドペーパーを使用して取り除くだけで大丈夫です。
一方で大きなささくれや、目に見えない亀裂の疑いがある場合は、竹刀を一度分解して内部まで確認することをおすすめします。
竹刀削りを使う際のポイントは、竹に対して直角に近い角度で刃を当て、削る方向を一定に保つこと。
削り終わったらサンドペーパーで滑らかに仕上げ、最後に布に少量の竹刀油を含ませて全体を軽く拭くと、乾燥を防ぎ破損しにくくなります。
竹刀を組み替えるときのコツ
竹刀を組み替える際には、まず竹刀を分解し、4本の竹をつなぐ「契(ちぎり)」を取り出します。
新しく入れる竹の溝(ミゾ)が契に合わない場合は、ノコギリなどを使って新しいミゾを作ります。
このとき、ミゾがきつすぎると契が入らず、逆に緩すぎるとしっかり固定できません。
いきなり深く削らず、少しずつ様子を見ながら調整していくのがコツです。
打突側を回して使うのは逆効果
中には「竹を回して使えば竹刀が長持ちする」と考える人もいますが、これは逆効果です。
普段加わっている力とは反対方向に力がかかることで、竹の繊維に無理な負担がかかり、かえって壊れやすくなります。
・先革
先革に穴が空いたり、破れそうになったりしていないか見ます。これにより竹が飛び出す危険性を防ぎます。 穴があいていたり擦り切れそうなものは、すぐに新しいものに交換します。また先革の太さは財団法人全日本剣道連盟の定める、剣道試合・審判規則第3条、細則第2条(1.2)で規定されていますので、年齢などを考慮し、自身に適したサイズのものを使用しましょう。
・中結
中結は緩んでいないか、また切れそうになっていないかを確認します。中結の役目は4本の竹がバラバラになるのを防ぐことです。中結が緩いと先革も外れやすくなりますので気をつけましょう。 緩みがある場合には、しっかりと締め付けます。また最後結びきれずに先端が余ってしまった場合には、はさみで適当な長さに切ります。
・弦
竹刀がしなる際に、バラバラになるのを防ぐ役目を持つのが弦です。緩いと打突時に先革が外れる可能性がありますので、ピンと張った状態であるか確かめます。 緩んでいれば、締め直します。柄革や弦自体も使用していくうちに伸びるものなので、定期的に締め直すことを心がけましょう。
・柄革
柄革が緩いと手の内の冴えが十分竹刀に伝わりません。パフォーマンスを上げるためにも、竹刀に合った柄革を使用します。 使用していくうちに緩んできたら新しいものに変えましょう。また再利用したい場合には熱湯を少しかけ、革を収縮させます。乾くと多少すべりやすくなるので、革をしごいてなじませます。
購入後の手入れ方法
破損があった際の手入れも大事ですが、新しく買った竹刀も、予め手入れをしておくことで良い状態を保つことができます。
・通気 湿度
竹刀購入後は、湿気の少ない、通気性の良い場所で保管します。また温度の上がりにくい、常温の場所が良いでしょう。更に手間はかかりますが、保管時には付属品も外した方がより効果的です。なぜなら付属品に使われる革はホルマリンなどの化学薬品を使っているため、つけっぱなしですと劣化を早める可能性があるからです。
・竹刀油
竹に油を染み込ませて何日かおいておくのも、竹刀の強靭さを保ち、長持ちさせるのに有効です。方法としては、ティッシュや脱脂綿に油を染み込ませたものを、竹刀の竹を一枚はがしたところから入れ、節に噛ませます。竹は節のところからしか油を吸わないためです。噛ませた後は、竹刀を組み直して糸で固定します。油が染み渡るまでには大体1ヶ月から2ヶ月程かかります。
油は専用の竹刀油というものがありますが、それ以外のものを使用する際には、竹と同じ植物性のものが良いでしょう。
油の代わりにろうを使う方もいるようですが、おすすめしません。なぜならろうは塗る際にムラができてしまいますし、稽古中に相手の防具に付着する可能性があるからです。一度ついたろうは落とすのが大変です。更に寒くなるとろうが剥がれ、床なども汚してしまう可能性があります。
まとめ
様々な竹刀の手入れ方法を紹介してきました。 ここまで読んでこられた方の中には、たくさんの手順があり、面倒だと思われた方もいるのではないでしょうか。
しかし、ただ強さを追い求めるだけではなく、竹刀の手入れを行うことで安全に配慮し、相手も慮ることができてこそ、「勝負の場においても礼節を尊ぶ」剣道家と名乗れるのではないでしょうか。
また、手入れを行うことで竹刀にも愛着が沸くなど、心の変化も起きるはずです。 常に手入れを怠らず稽古に励むことで、剣道の上達にもつながっていくことでしょう。







 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
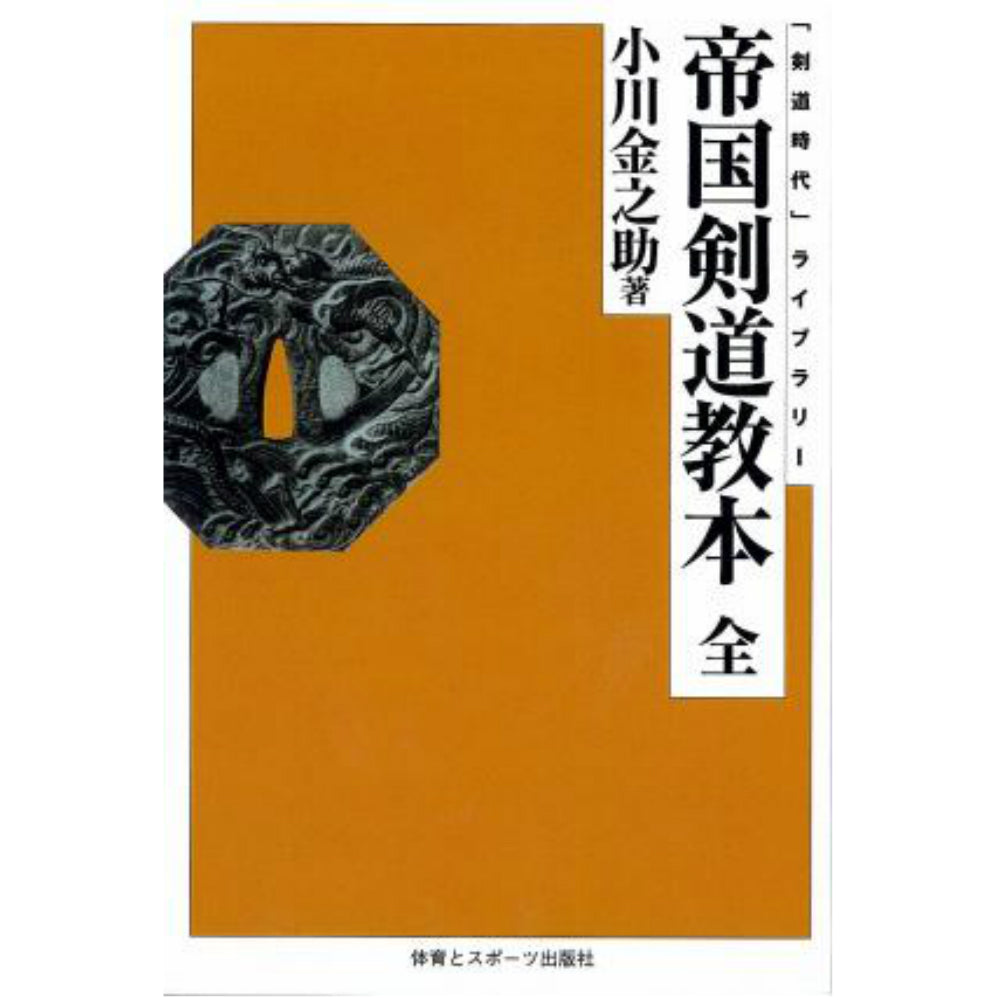 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 武扇
武扇
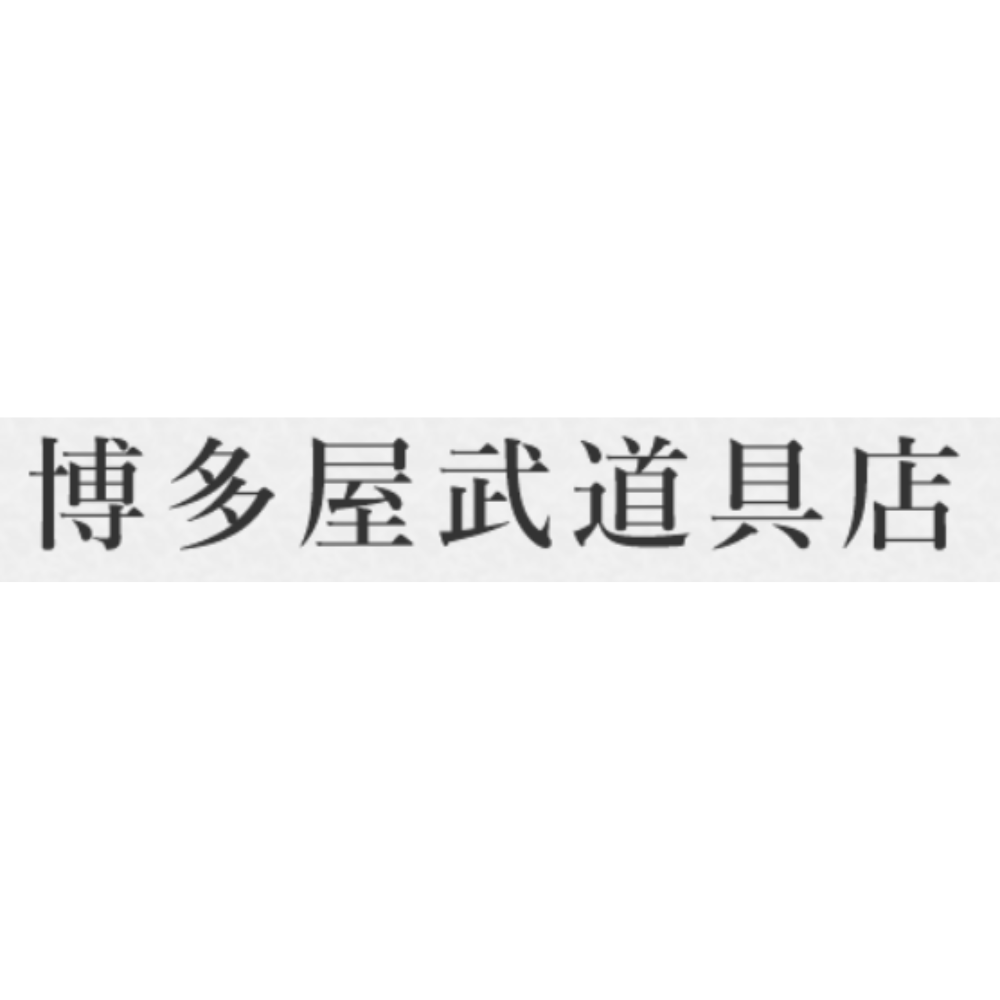 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ


 お得セット
お得セット
 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 タイヨー産業
タイヨー産業
 武扇
武扇
 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ
 インタビュー お役立ち記事
インタビュー お役立ち記事
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド
 GLOBAL SHIPPING GUIDANCE
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE