プロフィール
 株式会社西日本武道具
代表取締役 西淳二 氏
株式会社西日本武道具
代表取締役 西淳二 氏
譲れない竹刀作りへの想い
—御社はいつ頃から竹刀メーカーとして製品を販売されていらっしゃるんですか? 社長「竹刀に携わってからは30年以上になりますね。剣道防具の取り扱いは10年程前にスタートしました」 —竹刀づくりにかけるメーカーとしての想いを教えてください。 社長「現在流通している竹刀ですが、その大半は台湾の桂竹と言われている竹材です。 その他には真竹と表示されている竹刀もありますが、国産真竹なのか、中国真竹なのか、あまり明確になっていないことは課題と考えています。 良いとか悪いとかではなく、きちんと事実を伝えていくことはメーカーの役割であり大切なことだと考えています。中国真竹でも仕上げが良く素晴らしいものは沢山ありますし、もちろん国産には国産の良さがあります。 より多くの剣道家の方々に知っていただき、使っていただくことが私たちの使命であり、日本の竹刀職人を絶やさないという事に繋がると考えています」竹刀工場の見学

福岡の山深くにある、那珂川真竹工場
砂川「弊社ブランド『如水』の豊後材、『國祥』の京都材、
膨大な竹の削りかす
—職人さんは不足しているとお考えですか? 砂川「そうですね。全国でも数えるくらいしかいらっしゃいませんので」 ー御社の職人が製造技術を海外へ伝えていき、広げていくということはされないのでしょうか? 砂川「真竹工場で生産した竹刀は、京都は京都、豊後は豊後の竹の色の竹刀が出来るんです。職人さんそれぞれで乾燥の仕方も変わってきます。"焼き"の入れ方、矯め等の違いから、打った時の伝わり方も違ってくる。だから、ここでしか出来ないんです」 砂川専務
砂川専務
工場内へ

竹刀師 大橋茂正氏
砂川「約10年前、社長が真竹工場を作りたい、竹刀メーカーとして職人を育て残していきたいという”想い”を持っていました。 元々、大橋さんが『大和』という完全手作りの竹刀を作っていたこともあり、当社の”想い”の手伝いをしてもらうこととなり真竹工場がスタートしました。 そこで出来上がったのが”如水”という純国産真竹竹刀です」焼きの工程
大橋「竹を固めて強くする作業です。竹刀を形作る基本的な作業ですが、重要です。」
竹からは、煙が立っている
—前処理とは、こちらのことでしょうか? 大橋「そうです。職人が1番重要視している作業工程です。この工程がうまくいっていないと、最後までうまくいきません。4枚分を矯めるのが大体10~15分の間です。4枚1組で矯めます。4枚をワンセットで最後まで作業をしていく、もう最後までですね。……これが竹の油です」
艶やかな竹
—自然に出てくるんですか? 大橋「そうです。この状態が職人用語で『竹がわいた』と言います。湯気が出てますでしょ?繊維から水分が出てくるんです。この水分の出具合と皮の油の出具合で、竹の焼け具合を判断します。これを伸ばして、成型します。焼き過ぎてもいけないし、焼きが足らないのもいけない」若手職人の育成
ーお二人はなぜ、竹刀職人になろうと思われたのでしょうか? 田村「竹刀を作ることを見たことがなかったですし、そういう環境が少なかったので、単純にやってみたいという興味がありました。元々剣道をやっていたので。」 日下「私は、とにかく自分でやってみたいという好奇心もあり飛び込んでみました」
大橋氏の後進 日下一喜さん(左)、田村侑也さん(右)
—どういうところにやりがいがありますか? 日下「初めて作った時は、竹の状態から竹刀の形になるだけでも嬉しかったですね」 田村「ものの状態が良いと営業担当からフィードバックをもらえると嬉しいですね。あとはお客様が喜んでくれたりしたときです」 —いつかお二人が後進を育てていかれるのが楽しみです。本日は、ありがとうございました。
—いつかお二人が後進を育てていかれるのが楽しみです。本日は、ありがとうございました。
 今回インタビューを受けていただいた西日本武道具さんの商品ページはこちら!
インタビュアー
◎代表取締役 上島 郷
今回インタビューを受けていただいた西日本武道具さんの商品ページはこちら!
インタビュアー
◎代表取締役 上島 郷
 1987年生まれ仙台出身。仙台高校剣道部時代に佐藤充伸氏に師事、インターハイベスト8。
大学卒業後、全米で200店舗展開する外食チェーン店の事業開発責任者を務める。外資インターネット広告運用企業での営業職、株式会社イノーバで営業部・社長室リーダーを経て、2017年1月にBushizo株式会社を設立。
◎取締役 工藤優介
1987年生まれ仙台出身。仙台高校剣道部時代に佐藤充伸氏に師事、インターハイベスト8。
大学卒業後、全米で200店舗展開する外食チェーン店の事業開発責任者を務める。外資インターネット広告運用企業での営業職、株式会社イノーバで営業部・社長室リーダーを経て、2017年1月にBushizo株式会社を設立。
◎取締役 工藤優介
 1984年生まれ北海道出身。 立教大学法学部卒業。在学中にはフリーマガジンの創刊、アパレルブランドのマーケティング支援を携わる。2008年ヤフー株式会社へ入社。検索連動型広告・ディスプレイ広告などの広告商品の営業に従事。2017年1月にBushizo株式会社を設立。 6歳から剣道を始め現在に至る。
1984年生まれ北海道出身。 立教大学法学部卒業。在学中にはフリーマガジンの創刊、アパレルブランドのマーケティング支援を携わる。2008年ヤフー株式会社へ入社。検索連動型広告・ディスプレイ広告などの広告商品の営業に従事。2017年1月にBushizo株式会社を設立。 6歳から剣道を始め現在に至る。







 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
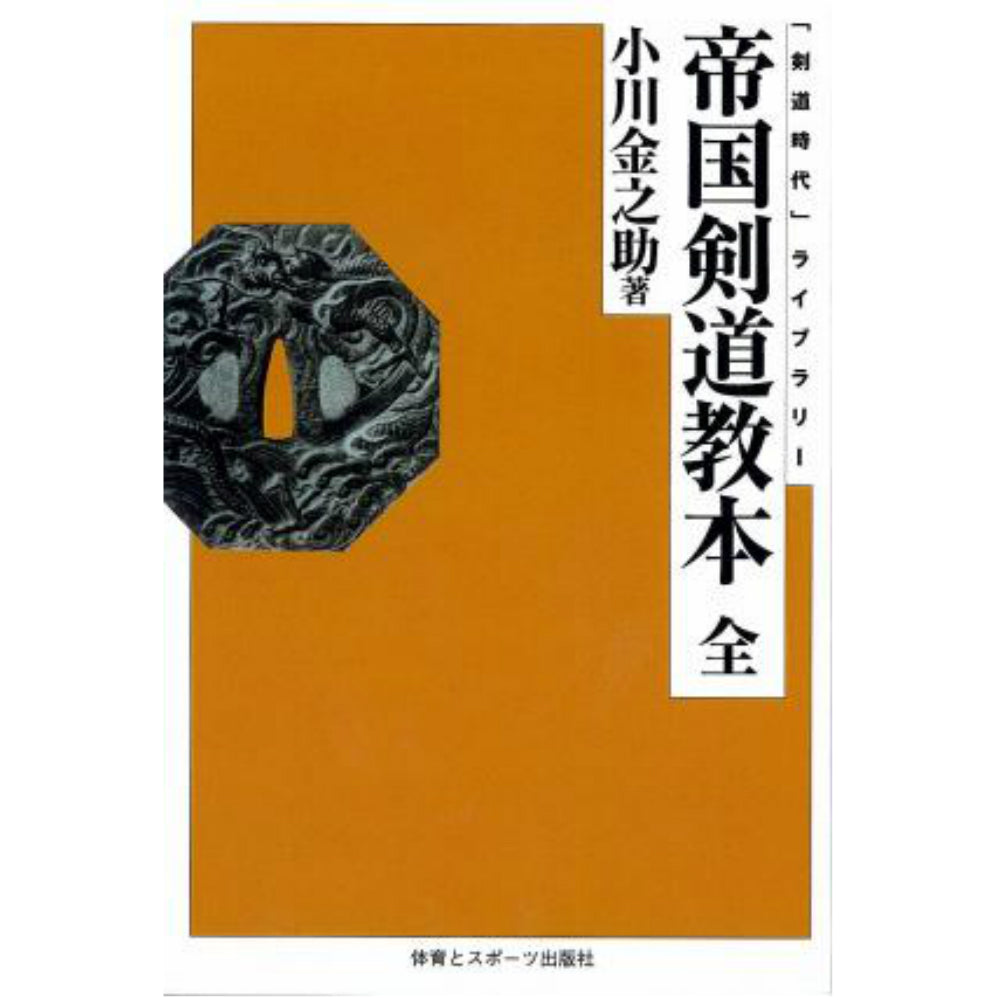 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 武扇
武扇
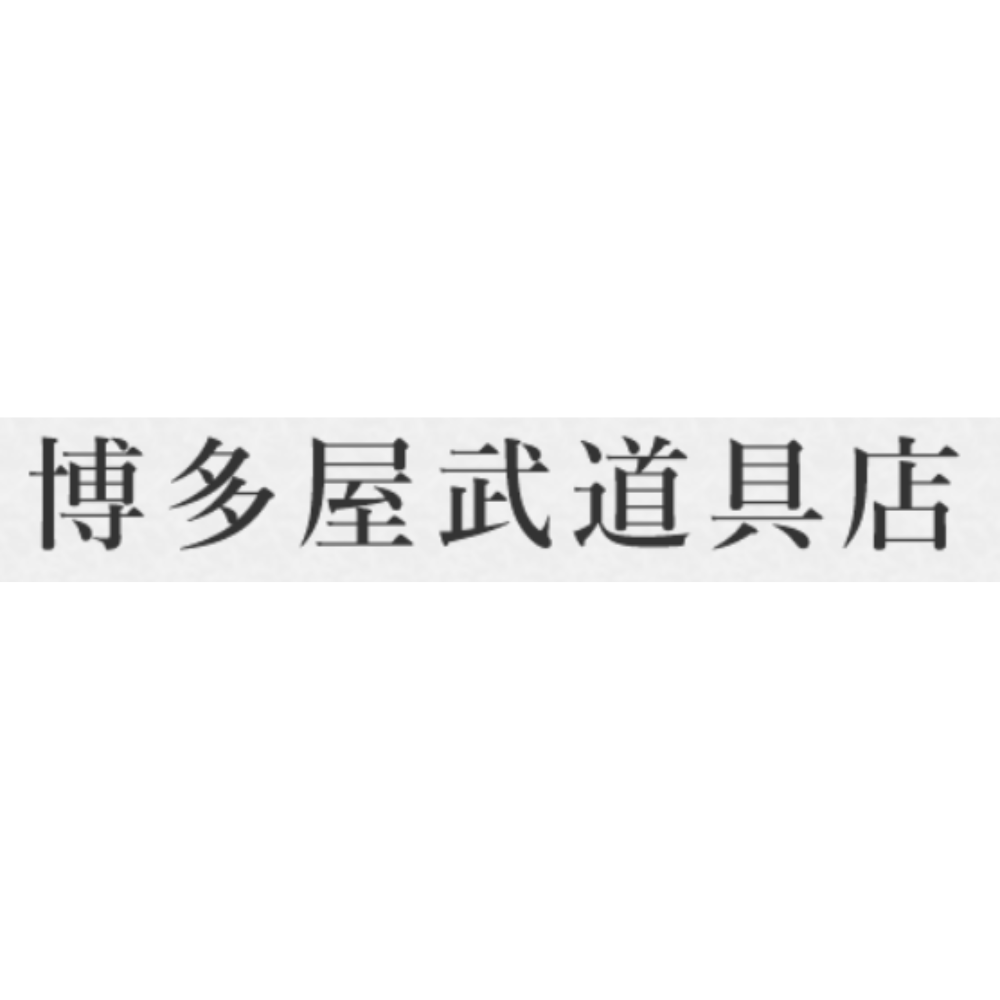 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ


 お得セット
お得セット
 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 タイヨー産業
タイヨー産業
 武扇
武扇
 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ
 インタビュー お役立ち記事
インタビュー お役立ち記事
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド
 GLOBAL SHIPPING GUIDANCE
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE










