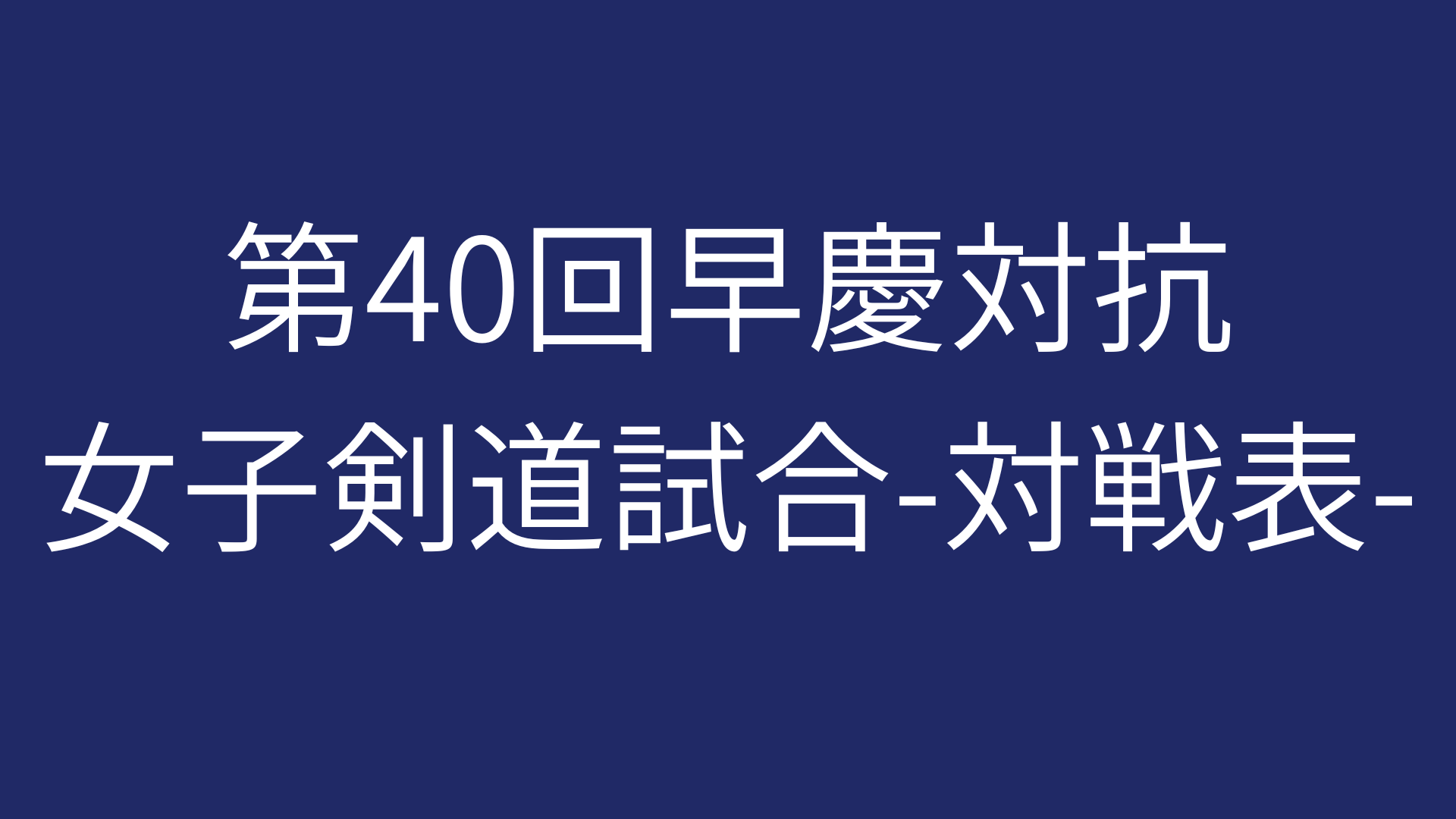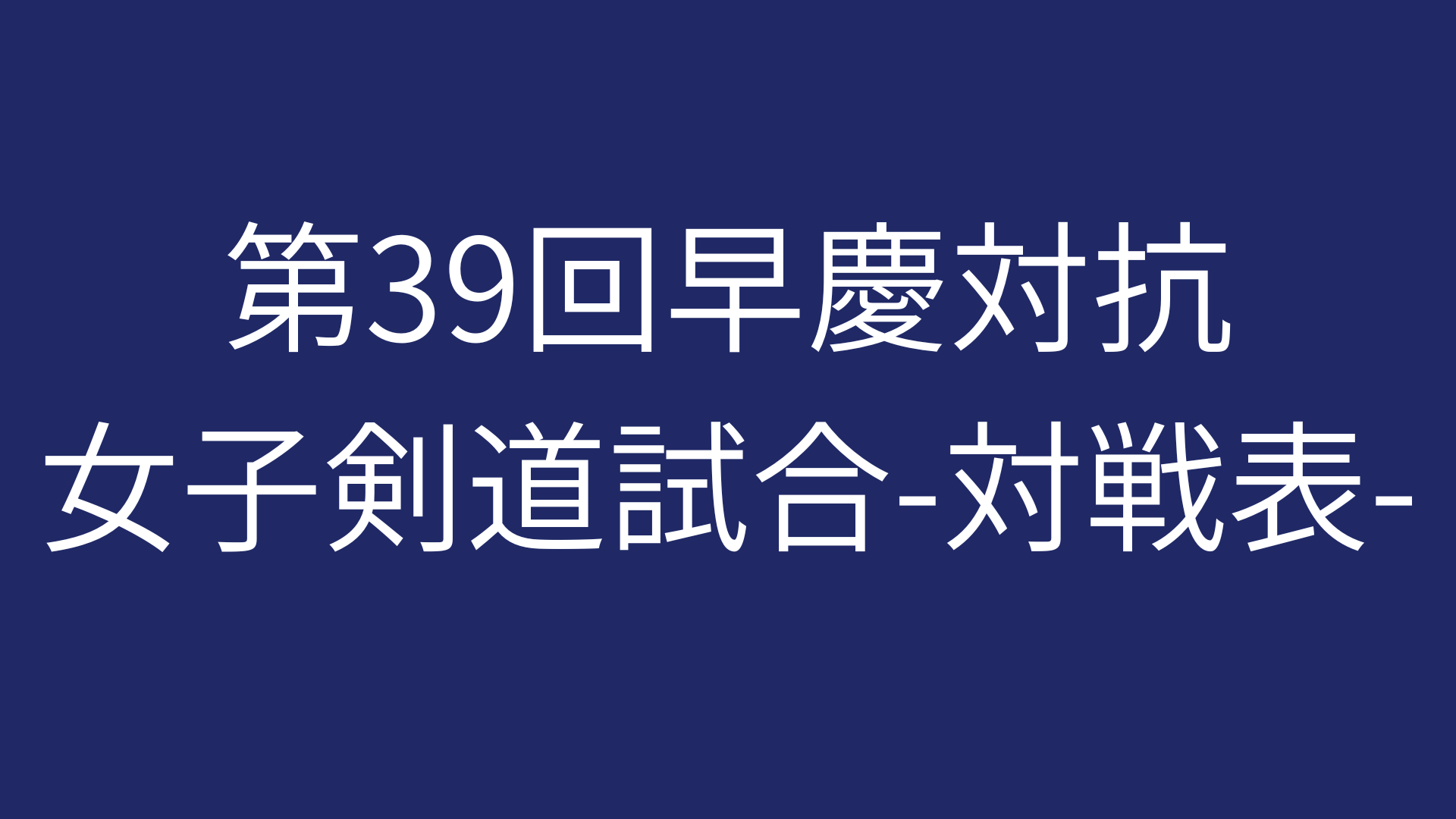終礼を終えると、大人たちに囲まれた。湊、鈴木、中倉、そして森田という男。
「どうも、森田といいます」
彼は元会社員で、昨年早期退職したばかりだという。
「今は無職ですが、道楽で剣道をやっとります」
「森田先生は六段なんですよ」
鈴木の紹介に、本人は謙遜してみせた。
「もう十年も六段のまんまなんですよ。七段審査にさっぱり受からんのです」
あっはっは、と森田はひとりで笑った。
子どもと保護者が帰宅した後、駅前の居酒屋で男五人の宴会がはじまった。ポロシャツ姿の森田以外は全員がスーツを着ている。鈴木はスーツが小さいのか、生地が張りつめていた。左手の薬指には控えめな指輪をはめている。
「私は区役所の税務課で働いてます。去年までは生涯学習支援の仕事をしてたんですけどね」
「役所は異動が多くて大変でしょう」
中倉が唐揚げをかじりながら言った。
「まあね。でも区の外になることはないから、道場運営には都合がいい」
「運営っていっても、この人月に五百円しかとってないんですよ。人がいいというか何というか」
鈴木は中倉に指さされながら、笑ってビールを傾けている。
「本当はタダでもいいんですけど、中倉さんが金とれってうるさいから」
「タダだと逆に気を遣うんだよ」
ふたりは年が近いせいか、親しそうに見える。
「中倉さんはかなり前から道場に通ってらっしゃるんですか?」
「私? 道場がはじまった時だから、五年目かな。だから、私の剣道歴も五年目」
「それまでは剣道はまったく?」
「ええ。学生の時に野球はやってたんですけどね」
中倉は大きな腹を叩いてみせた。
「普段は会社勤めですか」
「そうですね。しがない会社員です」
「やだなあ、ほんとのこと言ってくださいよ」
湊が横から茶々を入れる。
「俺は大企業の事業部長だぞ、って。年収一億」
「バカ。役員でもそんなにもらってないぞ」
年収はともかく、大企業の事業部長というのは本当らしい。中倉から受け取った名刺には、確かに大手総合商社の事業部長と記されていた。中倉の勤務先に比べれば、シマエ商事など吹けば飛ぶような会社だ。よく見れば、中倉のスーツや革靴は、目立たないながらも仕立てのよさが感じられた。
「息子と一緒に剣道をはじめたんですよ。たまには運動しなきゃ、と思ってね。この間二段に合格したんだけど、嬉しかったなあ」
「俺も早く七段合格してえなあ」
森田が呻くように言った。
「七段審査は四カ月後ですか。頑張ってください」
「そりゃそうですよ。これだけが私の道楽なんだから」
鈴木の励ましに応じつつ、冷酒をあおっている。湊はとっくりを横取りし、自分も冷酒を味わっている。
「森田さんも会社勤めされてたんですよね」
「中倉さんとこみたいな有名企業じゃないけどね。冷蔵庫の設計をしとりました」
今は柔和な目突きだが、時おり見せる鋭い視線は、技術者としての頑固さや厳しさを伺わせる。
「剣道は大学生の頃にはじめたんですがね。弱くても長いことやってりゃあ、六段くらいまではいけるもんですね」
湊が追加のとっくりを注文した後、会話に割り込んだ。
「弱いなんて。森田さん、試合ではかなり勝負強いんですよ」
どんな試合に出るんですか。そう訊こうとした時、鈴木が咳払いをした。
「ではそろそろ、本題に入ろうかな」
鈴木は少し硬い顔をしている。見ると、中倉、湊、森田も緊張の面持ちだった。自分ひとりが事情を知らないらしい。
「本題って、何です?」
「浦辺さんに、来月の道場対抗に出場してほしいんです」
「はい?」
「来月、都の道場対抗大会があるんですが、見ておわかりの通り、うちの道場には大人が四人しかいない。このままでは大人の部に四人で出場しなければならないんです。浦辺さん、ぜひ力を貸してください」
来月開催される道場対抗戦は年齢別に分かれているらしく、大人の部は大人だけで五人のチームを組まなければならないという。四人でも出場はできるが、ひとり分不戦敗となり、圧倒的に不利になってしまう。急な提案に動揺した。
「俺が出ても、使い物になるかどうか……」
口ごもっていると、四人がずずっと顔を近づけてきた。
「浦辺さん四段でしょ。私まだ二段ですよ」
「俺なんかもうすぐ還暦ですわ」
「大丈夫。今日の動きを見た感じ、いけます」
「また一緒に剣道やりましょうよ」
湊の言葉に違和感を覚えた。
「一緒に?」
「そうですよ。高校三年のインターハイ。同じ場所、同じ時に俺たち剣道してたじゃないですか。あの時は違う高校だったけど、今度は同じチームで」
湊の台詞は、心を大きく動かした。これも何かの縁だ。
「本当に俺でいいんですね」
「もちろん」
鈴木はそう言って、握手を求めた。少しクサいな、と思いながら、差し出された手を握り返した。中倉は「これで五人揃った!」と喜び、森田は「これでひとり分不戦敗しなくて済む」とあからさまに本音を漏らした。湊は満足げに頷いていた。
それからは翌月の大会に向け、足繁く道場に通った。週二回、水曜と土曜の稽古には必ず参加し、身体を痛めつけた。同僚からのフットサルの誘いも断った。日曜には剣道雑誌を読んだり、道場の子どもや保護者が開くバーベキュー大会に参加した。
剣道の感覚は徐々に戻ってきた。最初は上段の構えをとるだけで体力を使い果たしていたのが、二回、三回と稽古を重ねるにつれて、さまになってきた。湊や鈴木からいいように打ち負かされていた地稽古も、次第に渡り合えるようになってきた。
三週間が経った頃、篠田が不思議そうに問いかけた。
「浦辺さん、痩せました?」
「二キロ痩せた。最近、剣道再開したんだよ」
篠田はじろじろと身体を眺めまわした後、つぶやいた。
「何か引き締まりましたね、浦辺さん」
「どうしてお前はそんなに偉そうなんだよ」
篠田の頭を小突くふりをしながら、内心少し嬉しかった。
その日も道場で汗を流した後、湊とふたりで居酒屋へ行った。中倉と森田は欠席し、鈴木も用事があるから、と帰ってしまった。
「鈴木さんの家庭事情知ってる?」
湊は赤ら顔で冷酒をすすっていた。
「家庭事情って?」
「鈴木さん、奥さんと離婚寸前みたい」
初めて聞く話だった。
「実は俺も直接本人から聞いたわけじゃない。前に道場で電話してるの立ち聞きしちゃったんだよ。親権とか言ってたし、もう結構話は進んでるのかもね」
鈴木を皮切りに、湊は剣道仲間たちの私生活を喋りはじめた。
「中倉さんは仕事のストレスが半端じゃないらしいよ。これは本人が言ってたけどね。元々はお酒飲めない人だったんだけど、若い頃は接待で飲めないなんて言えなくて、無理やり飲んでるうちに慣れたんだって。今もしょっちゅう付き合いがあるから、痩せる暇がないなんて言ってたよ」
「森田さんは五年前に娘さんが嫁にいって、その寂しさを紛らわすために道場に通ってるんだってさ。前に奥さんが道場に来たことあって、そんなこと言ってた。その奥さんも今は入院中らしくて、看病に専念するために早期退職したみたい」
湊はそこで一旦黙り込んだあと、ぽつりとつぶやいた。
「俺だって……」
そう言った後、湊は「なんでもない」と言って日本酒をすすった。









 手刺防具
手刺防具
 ミシン刺防具
ミシン刺防具
 小学生用
小学生用
 初心者向け
初心者向け
 日本製
日本製
 洗えるジャージ素材
洗えるジャージ素材
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 小物
小物
 竹刀袋
竹刀袋
 防具袋
防具袋
 ギフト
ギフト
 ファッション
ファッション
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド