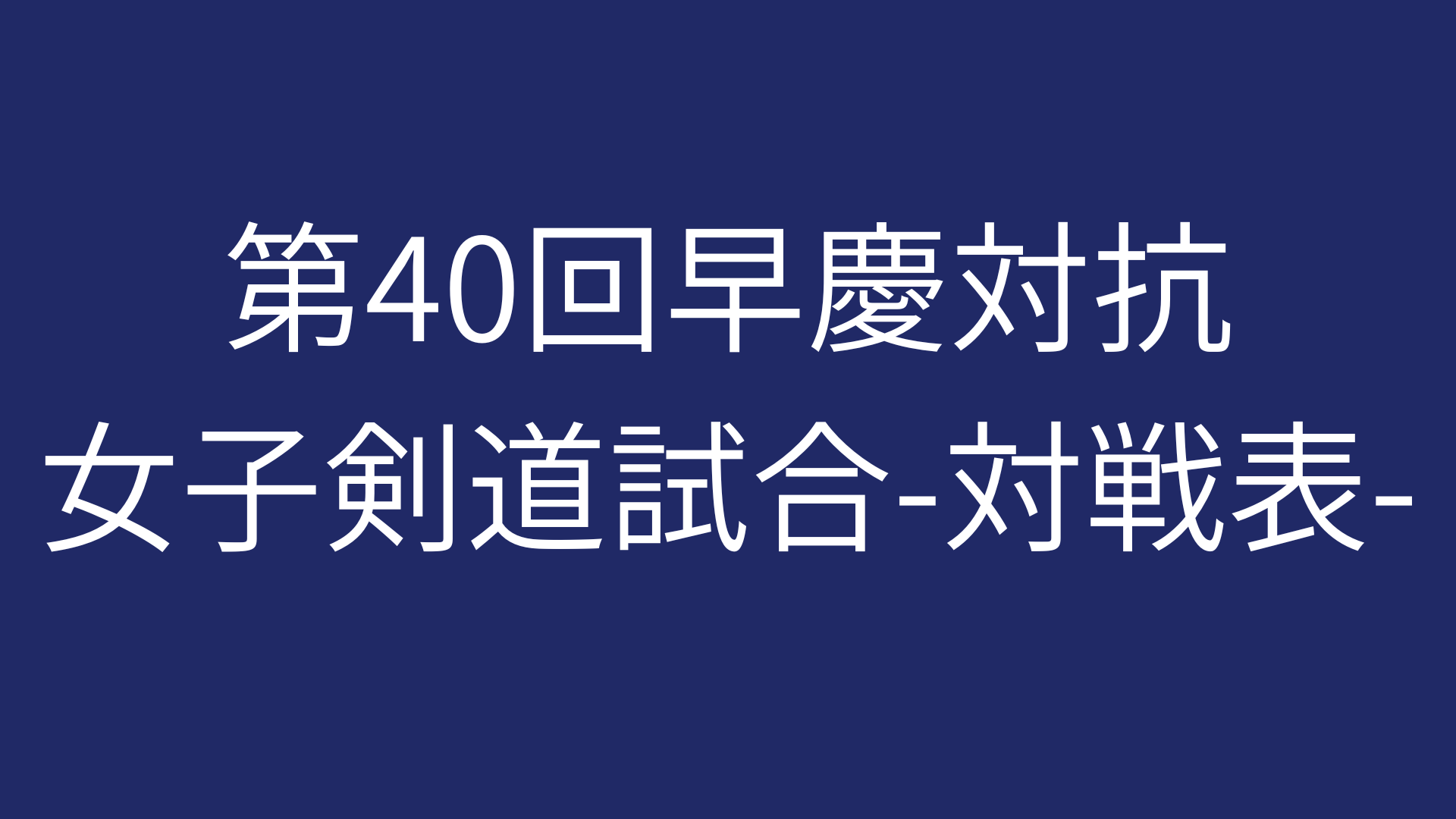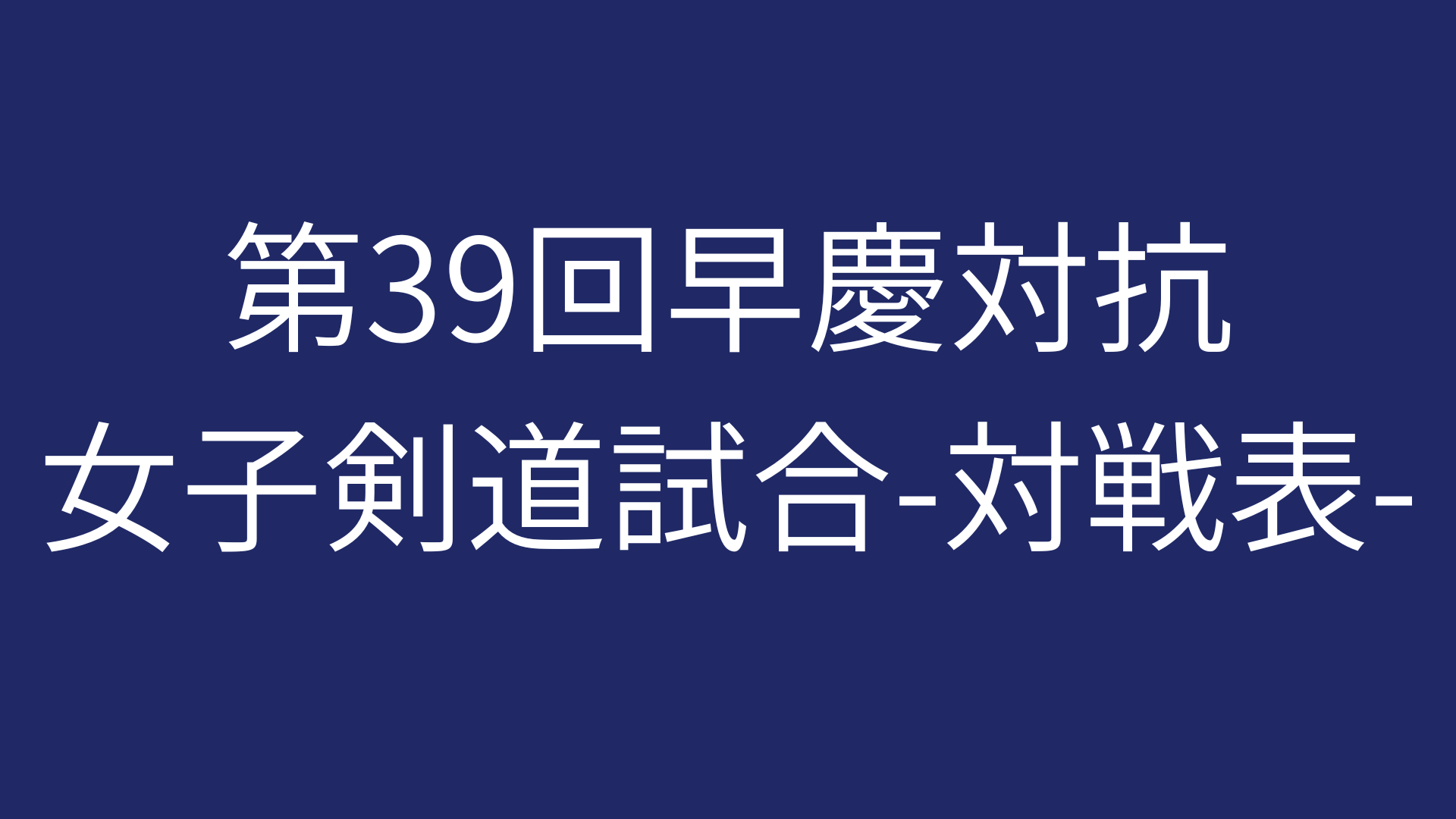会社に戻った時には八時を過ぎていた。職場にはぱらぱらと人が残っている。篠田は「腹減ったー」と言いながら、デスクの引き出しからカップ焼きそばを取り出した。まだ片づけなければならない仕事が残っている。パソコンを立ちあげると、十数通の電子メールが届いていた。思わず溜め息が出る。ついでに腹も鳴った。
「浦辺さん、お腹大丈夫ですか?」
篠田は早くもできあがった焼きそばを割り箸ですすっている。塩焼きそばの香ばしい匂いが鼻腔に入りこんできた。
「これと同じやつでよかったら、あげますよ。僕の奢りっす」
篠田から奢られるのはいい気分ではないが、空腹には替えられない。「ありがとう。ひとつくれ」と素直に告げた。
一緒に焼きそばをすすっていると、篠田がぽつりと「この間の飲み会、どう思いますか」と言った。
「先週の金曜か?」
篠田は黙って頷いた。先週の接待を指しているのはすぐにわかった。
「態度も横柄な感じだし。そもそも末端に口出ししてくんな、って感じじゃないですか」
麺をすすりこみながら、「まあそういうな」とおだててみた。まだ配属されてひと月だというのに、篠田はいっぱしの社員を気どって憤慨していた。
確かに、その原料メーカーの重役はいけ好かない人物だった。突き出た腹には自己愛と傲慢さがたっぷり詰まっていそうだ。
「まるで自分が一から開発した、みたいな言い方でしたよね。そんなわけないのに」
「まあいいだろ。売れ行きはいいんだから、苦労した甲斐はあるよ」
苦労したのは篠田じゃなくて、主に俺なんだけどな。とは言わない。
面倒なこともあるが、営業の仕事は概ね面白かった。高校までは社交性に欠けていたと自分でも思うが、大学に入って人づきあいを学んでからは、他者との交流が苦ではなかった。それどころか、会社員になってからはコミュニケーションを円滑に進めて事業を成功させる面白さに目覚めた。
ただ、土日にひとりでいる瞬間にふと思うこともある。
俺は本当にこのままでいいのだろうか。
翌週、化粧品メーカーの製造担当者からメールが届いた。新製品の口紅が予想以上の売れ行きで、急遽原料の仕入れ量を増やしたいという。こういう時、最終製品の作り手と原料の作り手の間を取り持つのが、シマエ商事の仕事だ。さっそく篠田に指示し、原料会社の担当者に連絡させた。
「浦辺さん、帝都化学の担当者なんですけど」
最近、篠田は敬語を直すよう努力しはじめた。
「吉村さんだろ?」
「それが、最近異動で担当が変わったらしいんです。新しい担当の人が、挨拶がてら直接会って打ち合わせがしたいって」
「じゃ、日程調整してくれ。打ち合わせも全部篠田に任せる」
「そんなあ」
「帝都化学は超お得意様だぞ。くれぐれも気をつけろよ」
「ビビらせないでくださいよ」
今回の取引を任せることで、篠田に自信をつけさせようと考えていた。帝都化学は長年の付き合いがある重要な取引先だが、だからこそ早いうちに慣れさせたいという狙いもあった。
打ち合わせ当日、出社するなり篠田は真っ青な顔で歩み寄ってきた。嫌な予感がする。
「浦辺さん、ヤバいっす」
敬語が元に戻っていることにも気付いていない。
篠田の話によると、取引先のメーカーに間違った原料情報を伝えてしまい、そのせいで製造が遅延しているという。
「先方はどんな感じなんだよ」
「めちゃめちゃ怒ってます」
溜め息をついた。
「とにかく主任が来たら、すぐに報告しろ。帝都化学との打ち合わせは俺が行くから、篠田はそっちの対応を優先しろ。後で俺も手伝うから」
事情を聞き、いくつか指示を出す。篠田はかすれた声で、すいません、と言って自分の席に戻った。対応が落ちついたら慰めてやろう、と思った。「若手社員はミスの数だけ成長する」というのは、新入社員の頃に今の主任から言われた言葉だ。
篠田から資料を受け取り、帝都化学との打ち合わせにひとりで臨んだ。社屋のエントランスに向かいながら、新しい担当者の名前を聞き忘れたな、と気付いた。まあいい。名刺を交換すればわかることだ。ベンチにスーツ姿の男がひとり、腰かけていた。近付くと、さっと立ち上がった。
「篠田様ですか?」
「いえ……申し訳ありませんが、篠田が業務上の都合で急遽出席できなくなりまして。本日は代理で私、浦辺が対応させて頂きます」
「そうですか。浦辺様ですね。私、帝都化学の湊と申します」
湊は短髪の似合う好青年だった。がっちりとした体型はスポーツで鍛えたものだろうか。会議室へ案内した後、改めて湊と名刺を交換した。湊大吾。真新しい名刺を眺めながら、どこかで見た覚えのある名前だと思った。湊も同じ思いらしく、まじまじとこちらの名刺を見つめている。
「失礼ですが」
先に口を開いたのは湊だった。
「おいくつですか」
「二十八です。もしかして」
「ええ。私も先日二十八歳になりました」
しばしの沈黙の後、今度はこっちが言った。
「……剣道、やってました?」
湊が名刺から、がばっ、と顔を上げた。
「インターハイ!」
湊はそう言ってから、あ、いえ、失礼しました、と慌てて謝った。
「浦辺さん、確か高三のインターハイで個人三位でしたよね」
「まあ……湊さんも、上位でしたよね。たしか北海道の」
「そうです、そうです。準々決勝で藤波幸太に負けました」
「うわ、懐かしい。久しぶりにその名前聞きましたよ。彼、今頃どうしてるんでしょうね。大学に行ったことまでは知ってるんですが」
「藤波は今、フランスですよ」
「フランス?」
「大学を出た後、剣道普及のためにフランスに渡ったんですよ。もう引退したけど、妙法学園の緒方先生っていたでしょ。あの人が今フランスで道場を開いているんですけど、そこに押しかけたそうです。アルバイトをしながら、道場で向こうの人に剣道を教えてるみたいですよ。今もまだあっちにいるはずですが」
初耳だった。
「浦辺さんは、今はもう剣道はされてない?」
「そうですね。大学で終わっちゃいました。湊さんは浪体大でしたっけ?」
「よくご存知ですねえ」
「だんだん思い出してきた。あの頃の浪体大は無敵でしたね。まだ剣道は続けてるんですか」
「やってますよ。人並み以上にできるのは、剣道しかないですから」
そこで一旦言葉を切った。
「今度、食事でもいきますか?」
そう言ったのは湊だった。
「私も同じことを思ってました」
「とりあえず今日は仕事の話にしましょう。私のプライベート用の携帯番号をお教えします」
湊は新しい名刺を取り出し、その裏に数字を書いて渡してくれた。同様に、携帯電話の番号を書いた名刺を差し出す。湊の顔には無邪気な笑みが浮かんでいた。
「じゃあ、言いだしっぺなんで、私から連絡しますね」
湊はそう言った後、鞄から分厚い封筒を取り出した。
「それで、今日は挨拶ではあるんですが、ちょっとご相談したいこともありまして。最近の仕入れ値推移をここにまとめたんですが……」
一瞬で仕事用の顔つきに戻った湊に合わせて、表情を引き締めた。
湊からの連絡はその日のうちに来た。銀座によく行く店があるから、そこで夕飯でもどうか、という誘いだった。指定された日はフットサルの予定が入っていたが、キャンセルして湊との食事に行くことにした。
数日後、店に行くと既に湊が来ていた。湊は律義につまみだけをちびちび食べながら待っていた。
「すいません、お待たせして。先に飲んでくれてよかったのに」
「いや、私がお誘いしましたから」
生ビールで乾杯した後は、一人称が私から俺に変わり、口調も少しずつくだけていった。牛乳に浸したビスケットが崩れるように、気持ちがほろほろと緩む。
「湊さんがいた頃の浪体大って、本当に強かったよね」
「同期がよかったから。石坂が大将やってましたからね」
「石坂翔は今、大阪府警ですよね」
「やっぱり詳しいなあ」
「高校卒業したら即、府警に入るって噂流れてましたよね」
「懐かしいねえ。結局、緒方先生に勧められて大学にいきましたけどね」
石坂翔は特別な存在だった。近況については、一度耳に入れば嫌でも覚えてしまう。それに、石坂が現在の剣道界でトップを走る有名選手だということもあった。
「一昨年は警察選手権で優勝。去年は全日本三位でしたっけ」
「そう。俺みたいな一介の実業団選手からすれば、遠い存在になっちゃったなあ、と思うけどね。次の世界大会も選ばれるだろうし」
ジョッキを傾けた。だとすれば、今や石坂翔はインターハイで一度戦っただけの自分とはほぼ無縁の存在だろうか。
「学生時代の湊さんのポジションは?」
「だいたい次鋒。でも俺たちの代は石坂と菊池のふたりがずば抜けてたから。俺なんかおまけみたいなもんだよ」
「菊池さんは今何を?」
「鹿児島で教員やってますよ。母校に戻って。体育教師のくせに美術室に入り浸ってるらしいです。あいつ、絵を描くのが趣味だから」
「お父さんが菊池守先生で、親子鷹って有名だったけど」
「そうそう。でももう親父さんは隠居してるみたい。今年、初めて自分が教えた生徒たちが全国に出るらしくて。今頃、猛稽古してるんじゃないかな」
湊は早々とビールから日本酒に切り替えていた。冷酒を湊のおちょこに注いでやる。
「実業団って、普通の社員に比べて仕事量が少なかったりする?」
「全然。むしろ普通以上に仕事してますよ。帝都化学の剣道部にはこういうモットーがあるんですよ。『剣道が強い奴は仕事もできる』って。仕事ができない奴は部内でもなめられるんです」
「厳しいなあ」
「浦辺さんはもう剣道しないの?」
湊は真っ赤な顔で尋ねた。
「もう長いことやってないからなあ。今やっても勝てないよ」
「そんなことないでしょ、腐ってもインターハイ三位なんだから」
腐っても、とは随分な言い草である。酒が入ってからの湊は、人が変わったかのようにくだけた口調だった。
「それに、こんなこと言ったら偉そうに聞こえるかもしれないけどね。剣道は勝つことだけが魅力じゃないと思いますよ」
おぼろげな記憶によれば、湊は高校生の頃、かなり汚い剣道をしていたはずだ。それこそ、勝つためだけの剣道だった。「勝つことだけが魅力じゃない」とは、その湊が言ったとは思えない台詞だった。
「よければ今度、俺の通ってるところに来ませんか?」
「実業団ですか。それは無理。足を引っ張るだけだから」
「いや、町の剣道教室ですよ。そっちにも週一回は顔を出してるんです。小学校の体育館を借りてやってるような、小規模な感じだから。小中学生ばっかりだし、初心者もいるし」
湊は熱心に誘った。帰り際、会計をしながら湊は言った。
「来週の水曜、どうですか。一緒に剣道しましょうよ」
何となく、やってみてもいいかな、と思いはじめていた。
「じゃあ行ってみようかな」
「ほんとですか? 嬉しいなあ。みんな喜びますよ」
どうして俺が行くとみんなが喜ぶのか。不思議だったが、詳しくは聞かなかった。









 手刺防具
手刺防具
 ミシン刺防具
ミシン刺防具
 小学生用
小学生用
 初心者向け
初心者向け
 日本製
日本製
 洗えるジャージ素材
洗えるジャージ素材
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 小物
小物
 竹刀袋
竹刀袋
 防具袋
防具袋
 ギフト
ギフト
 ファッション
ファッション
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド