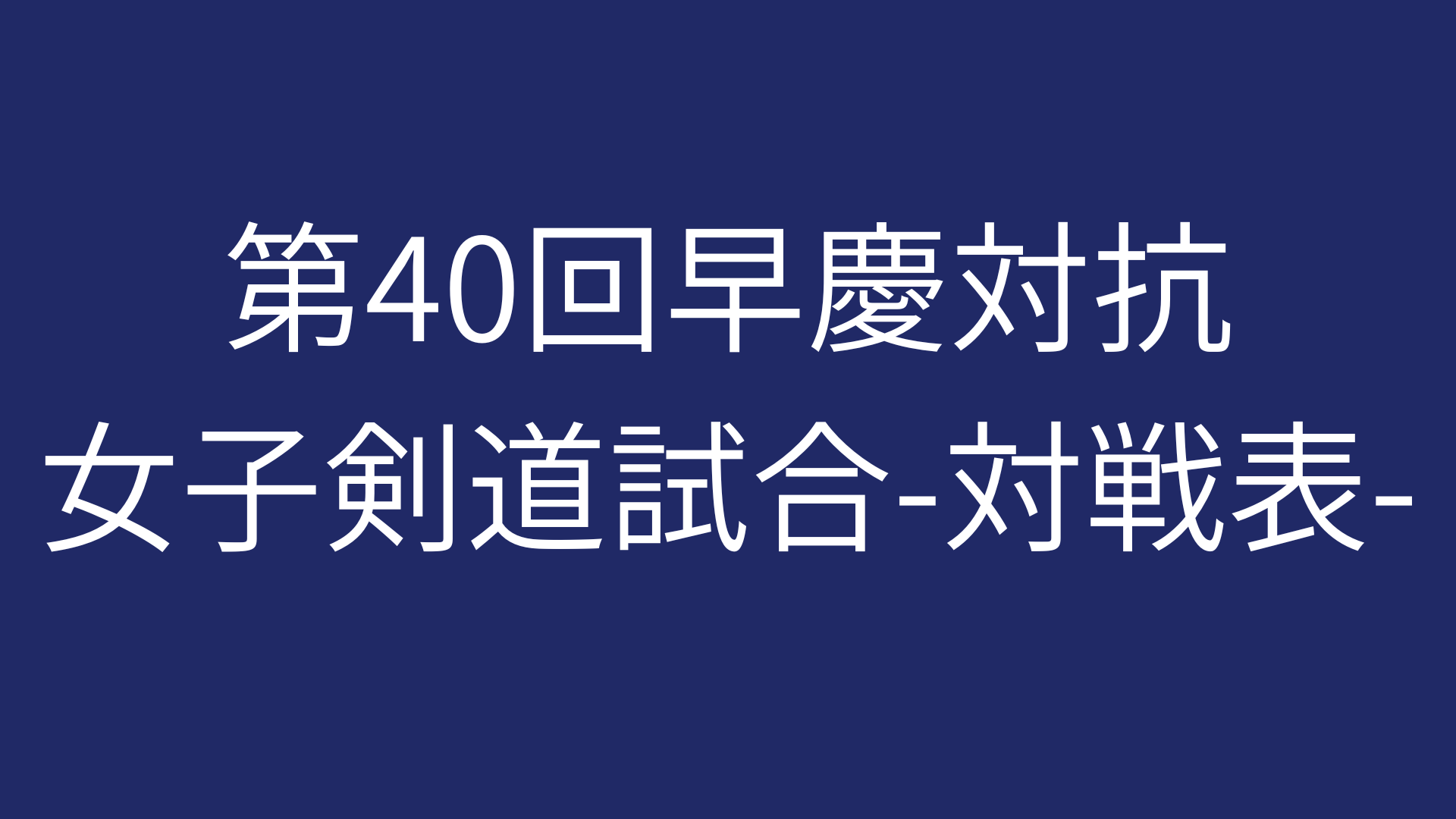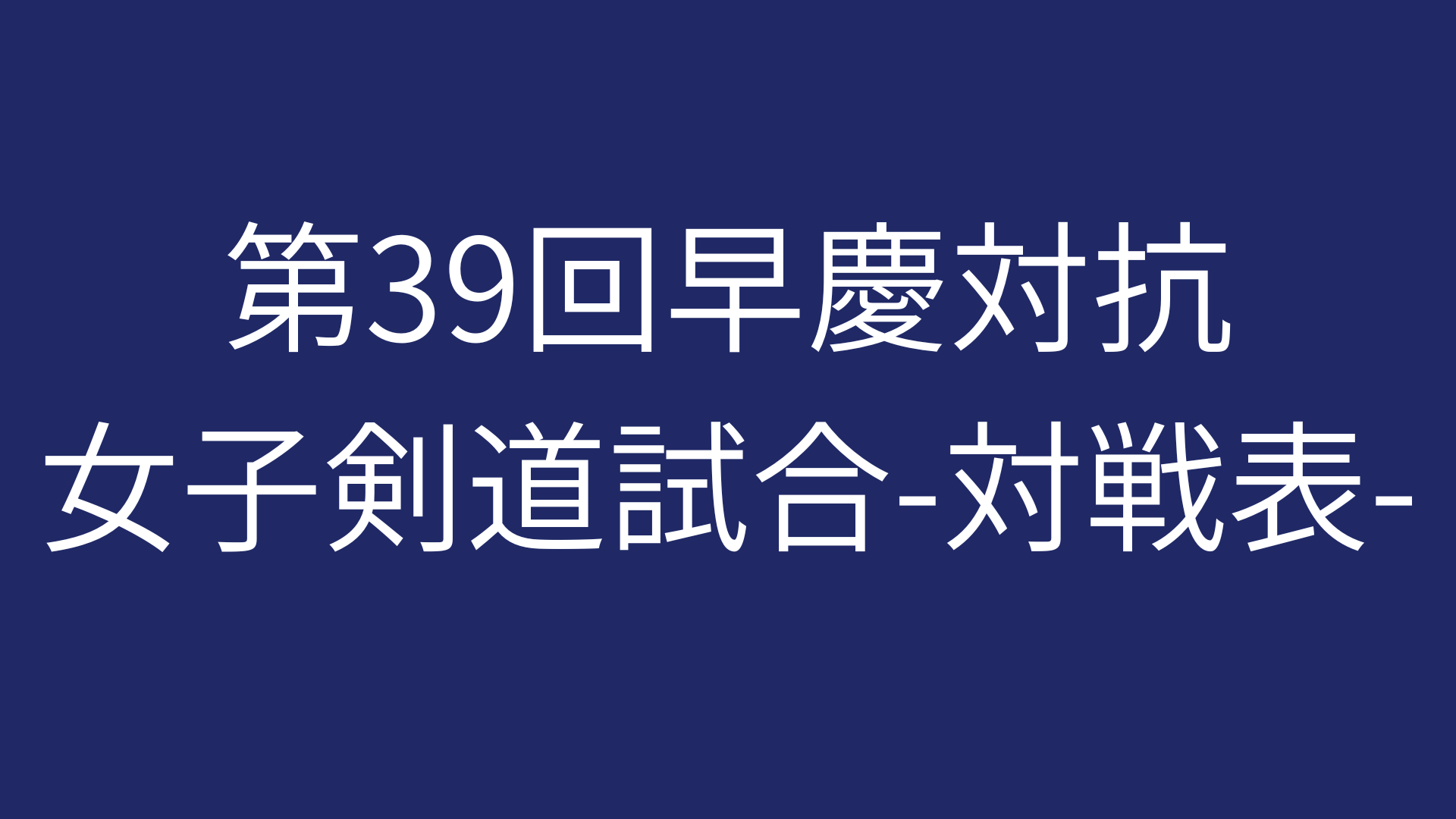五人目 浦辺元信
七月だというのに、梅雨の気配は色濃く残っている。ネクタイを緩め、首筋の汗をハンカチで拭いた。営業車の中には湿気が充満している。赤信号で停車中、運転席に座る後輩へ問いかけた。
「篠田」
「なんすか」
「お前、その敬語いつになったら直すの?」
新入社員の教育係に指名されたのは、昨月のことだった。篠田は研修を終えた直後こそ堅苦しい敬語を使っていたが、最近はすっかり緊張感がなくなっている。気づかぬうちに、髪の毛を少しだけ茶色に染めているようだった。
「僕の敬語、変っすか?」
篠田は助手席を一瞥もしない。もっとも、よそ見ばかりされても困るのだが。
「変だよ。その、何何っすかっていうの、やめろよ」
「僕、そんな風に言ってます?」
篠田は一向に自覚がないようだった。諦めて助手席のシートに深く身体を預けた。信号が青に変わり、営業車はゆっくりと発進した。二車線の左側を走る営業車を、後続の車が次々と追い越していく。
俺が新入社員の頃は、こんな運転してたら先輩に怒鳴られたけどな。なにトロトロしてんだ、って。しかしそんな説教は口にしない。そんなことを言えば、篠田は落ちこんでしまうだろう。今時の新入社員は繊細なのだ。
「浦辺さん」
「どうした?」
次は何を言い出すのかと恐れたが、続く篠田の台詞は予想外だった。
「浦辺さんって、何かスポーツとかされてたんすか?」
この質問は篠田なりの気遣いだろうか。確かに会話のない営業車は息詰まるような空気だった。拍子抜けして、溜めていた息を吐き出すと同時に答えた。
「剣道やってたよ。小学生から大学まで」
「今はやってないんですか?」
「うん」
そこで一瞬、間を置いた。最後に剣道をしたのがいつだったか、思い出していたのだ。
「社会人になってからは一回も竹刀触ってないな」
営業車は再び赤信号に捕まった。篠田はそろそろと停車線に近突き、寸分の狂いもなく停車した。この分だと、目的地に着くまでまだかなりかかりそうだな。大きなあくびをしながらそう思った。
新卒でシマエ商事に入社して、今年で六年目になる。シマエ商事は化学品を専門に扱う中堅商社である。売上の額こそ大手とは比較にならないが、専門性のある商品を取り扱っているのが強みだ。同じ分野には大手も参入しづらく、経営は安定している。この会社を選んだ理由はその安定があるからこそで、化学品自体に思い入れはない。
広島から上京したのが十年前のこと。学生時代は剣道以外、常に遊んでいた記憶しかない。今でも昔の遊び場である新宿や渋谷に行くと、学生時代の思い出が蘇ってくる。
就職活動では、エントリーシートの「部活動等の実績」という欄にいつもこう書いた。
(高校)全国高等学校剣道大会 男子個人第三位
(大学)関東学生剣道選手権大会 ベスト三十二
ボールペンでこの二行を書くたび、俺のピークは高校三年だったな、と思い返した。全国大会の準決勝で、石坂翔をあと一歩のところまで追い詰めたのだ。石坂といえば、当時学年では最強と目されていた。事実、準決勝を勝ち抜いた石坂はそのまま決勝戦でも勝利し、大会二連覇を果たした。
あの石坂と競り合った選手、という触れ込みだけで、推薦の声がいくつもかかった。その中から東京の私大を選んだ。学費が無料になることと、東京、という言葉への憧れがそうさせたのだ。
高校の監督はそれとなく反対した。あそこの大学はあんまり練習せんからなあ。それにちゃんと上段を指導できる人がいるかもわからんし。その声を聞き流し、上京した。
監督の話は確かに真実だった。進学した大学は有望選手を集める強豪ではあったが、高校以上の戦績を残せる選手は少なかった。新入部員の中でも特に期待を集めて一年からレギュラーとして試合に出場することができたが、最後まで目覚ましい成果を収めることはできなかった。
一方、石坂翔は大学生になっても世代のトップを走った。当初は高卒で大阪府警入りするという噂が流れたが、監督の助言で進学に切り替えたらしい。浪速体育大学に進んだ石坂は、大学生になってからも個人団体の両方で全国優勝を果たした。観覧席で石坂の試合を観戦しながら、剣道は大学でやめよう、と決めた。
剣道部OBのツテを頼って、大手企業に入ることもできた。しかしそうすれば、会社の剣道部に入部しなければならない。それは避けたかったから、自力で就職活動をしてシマエ商事から内定をもらった。
大学卒業以後、剣道はやめた。ただし防具と竹刀だけは、今住んでいるマンションに置いている。広島の実家に送り返すのが億劫なだけだ。
会社員になってからは、剣道以外の可能性を試してみたかった。勤めはじめた頃はよく逗子でダイビングをしていた。貯金など考えず、給料はあるだけ使った。最近は会社の同僚と一緒に銀座や大井町でフットサルをすることが多い。たまに女の子とも遊ぶが、特定の彼女はいない。結婚は三十歳を過ぎてからでいい、と思っている。
取引先からの帰り道、渋滞につかまった。カーラジオによると少し先の道路で玉突き事故が起こったらしい。死傷者はいないというが、事後処理には時間がかかるのだろう。
「全然進まないっすね」
篠田はハンドルに顎をのせて言った。お前の運転が遅いから渋滞に巻き込まれたんだよ、とは言わない。やがて退屈した篠田が話しかけてきた。
「浦辺さん、剣道どれくらい強かったんですか? 僕、自慢じゃないですけど高校の時にサッカーで県大会決勝までいきましたよ。決勝でぼこぼこにされましたけど」
「インターハイ個人三位」
げっ、と言って篠田が振り向いた。
「マジすか? めっちゃ強いじゃないすか。この間の歓迎会ではそんなこと言ってなかったじゃないすか」
「昔の話だよ。それよりお前、ほんとに敬語直せよ」
「すいません。でも全国三位かあ。すげえ」
篠田の見る目が少し変わったような気がした。しばらくすると、篠田がまた話しかけた。
「いつ剣道はじめたんすか?」
「小学校の三年」
「九歳かあ。僕なんか、何にも考えずに鼻水垂らしてましたね」
「俺だって何にも考えてなかったよ。小学生の時は弱かったしな」
「あ、そうなんすか。てっきり小学生の頃から強かったのかと思いました」
剣道をはじめた頃、広島には既に石坂翔という絶対王者が君臨していた。石坂は上級生たちを薙ぎ倒し、毎年のように県大会優勝をさらっていった。その石坂が、大阪の中学校へ進学した。名門である妙法学園の門を叩いたのだ。広島の中学剣道界は、にわかに群雄割拠の様相を呈した。しかしそんな状況でも、まだ目立った成績を残すことができなかった。
少しばかり名前が知られるようになったのは、高校の監督から上段の指導を受けてからだ。若い監督は自らも上段をとり、指導にあたってくれた。中段でやっていた頃が嘘のように、試合で勝てるようになっていった。
身長が高いわけでも、膂力が強いわけでもない。ただどういうわけか、右足よりも左足で踏み込む方が速く打突することができた。身体の構造上、そうなっているとしか思えない。
普通の左上段では、踏み込む足は左足になる。稽古前、遊び半分で上段を試していたところ、監督が驚いた顔で近づいてきた。
「お前、どこで上段習ったんだよ」
「いや、別に……」
「じゃあどうしてそんなに打つのが速いんだ」
上段を指導できる監督だったのは幸運だった。その日から監督に目をつけられ、マンツーマンでの特訓がはじまった。最初に指導されたのは上段の構え方。脇を締めろ、顎を引け、肘を緩めるな。稽古中に何度も怒鳴られていくうちに、少しずつ構えが様になってきた。その次は打突。まず小手を徹底的に練習し、続いてフェイントのかけ方を学んだ。
上段をとるということは、試合中は常に両手を頭上に掲げることを意味する。はじめたばかりの頃は、四分間腕を上げているだけで大量の乳酸が肩に溜まるのを実感できた。しかし毎日続けていれば何事も慣れるもので、上段でまともに試合ができるようになった頃には、肩の疲労はほとんど気にならなくなっていた。
上段が馴染んでくると、一本の取り方がわかってきた。最大の武器が打突の速さだということは知っていたから、トレーニングと素振りで更に速さを磨きあげた。すると更に相手から一本がとりやすくなる。先輩からは「浦辺の面打ちは、わかってても避けられない」といわれた。
ある日の稽古後、監督から「腕が長いな」と言われた。
監督の腕と比べてみると、五センチ以上長かった。身長は監督とほぼ同じだ。
「遠間からでも面が決まるわけだ」
確かに遠間からの面はよく一本になった。遠間からの一撃があれば、よりフェイントもかけやすくなる。身長の低さも多少はカバーできる。その時初めて、長い腕に生んでくれた親に感謝した。
市内大会での個人準優勝が、最初の入賞だった。それが高校二年の夏で、それからは立て続けに地方大会で成果を残した。監督も期待していたようで、毎週のように遠征を組んでくれた。
高校三年になり、部の主将に選ばれた。団体戦では県大会止まりだったが、インターハイ広島予選男子個人で遂に優勝を果たした。剣道部創設以来、初のインターハイ出場という栄誉までついてきた。
もし石坂翔が広島に残っていれば、と考えることはたびたびあった。石坂がいれば、とても自分は優勝できなかっただろう。今でもそう思っている。
本戦では面白いように面が決まり、気付けば準決勝まで進出していた。石坂は前の試合で足首を怪我していることもあり、これなら勝てるかもしれない、という驕りがあったのは間違いない。結果、あと少しというところで敗れた。石坂が片手突きを放った瞬間は今でも思い出すことができる。
「全部、昔のことだよ」
「なんすか?」
運転席の篠田が振り向いた。
「何でもない」
思い出から覚めても、まだ渋滞は続いていた。









 手刺防具
手刺防具
 ミシン刺防具
ミシン刺防具
 小学生用
小学生用
 初心者向け
初心者向け
 日本製
日本製
 洗えるジャージ素材
洗えるジャージ素材
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 小物
小物
 竹刀袋
竹刀袋
 防具袋
防具袋
 ギフト
ギフト
 ファッション
ファッション
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド