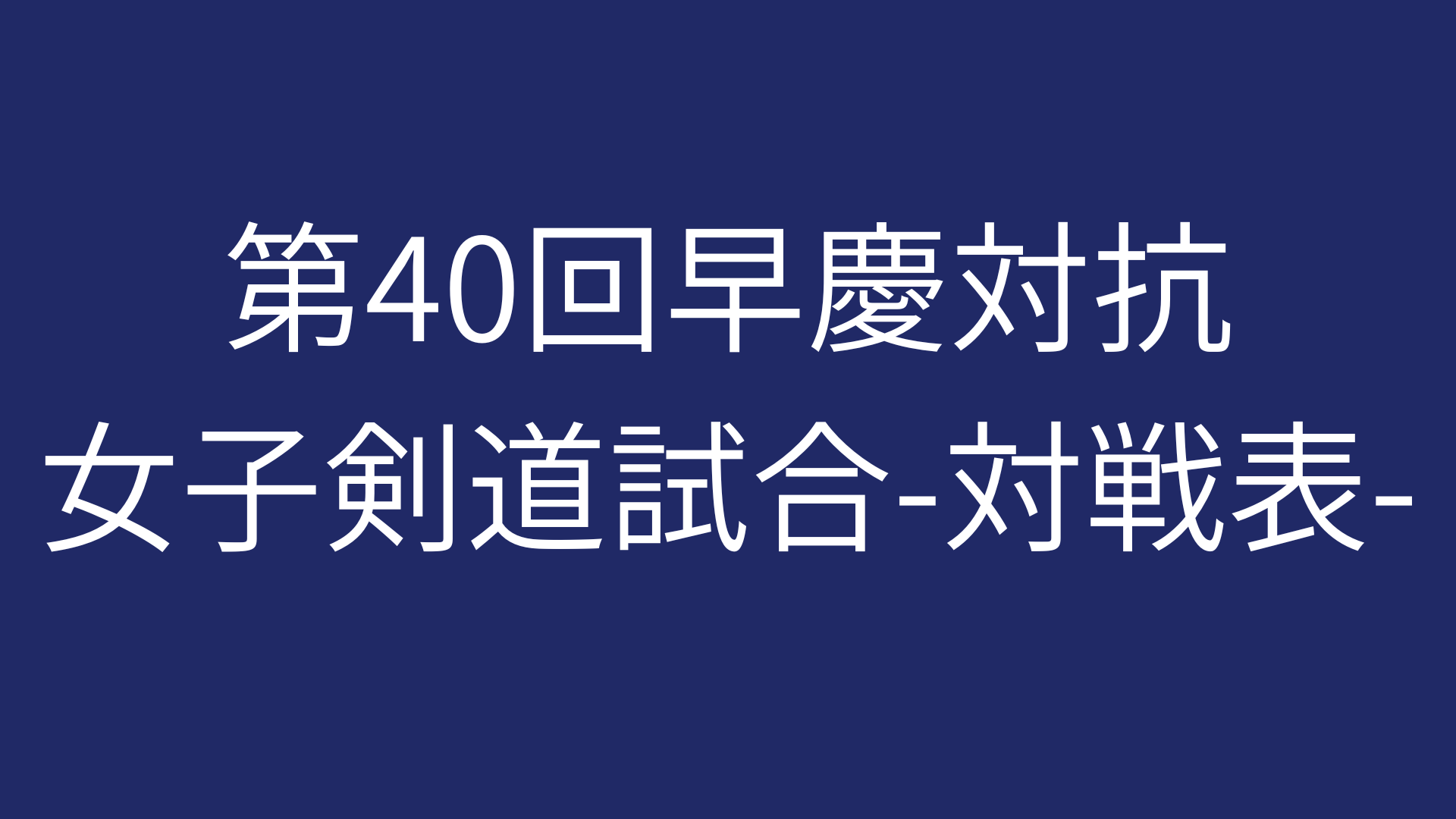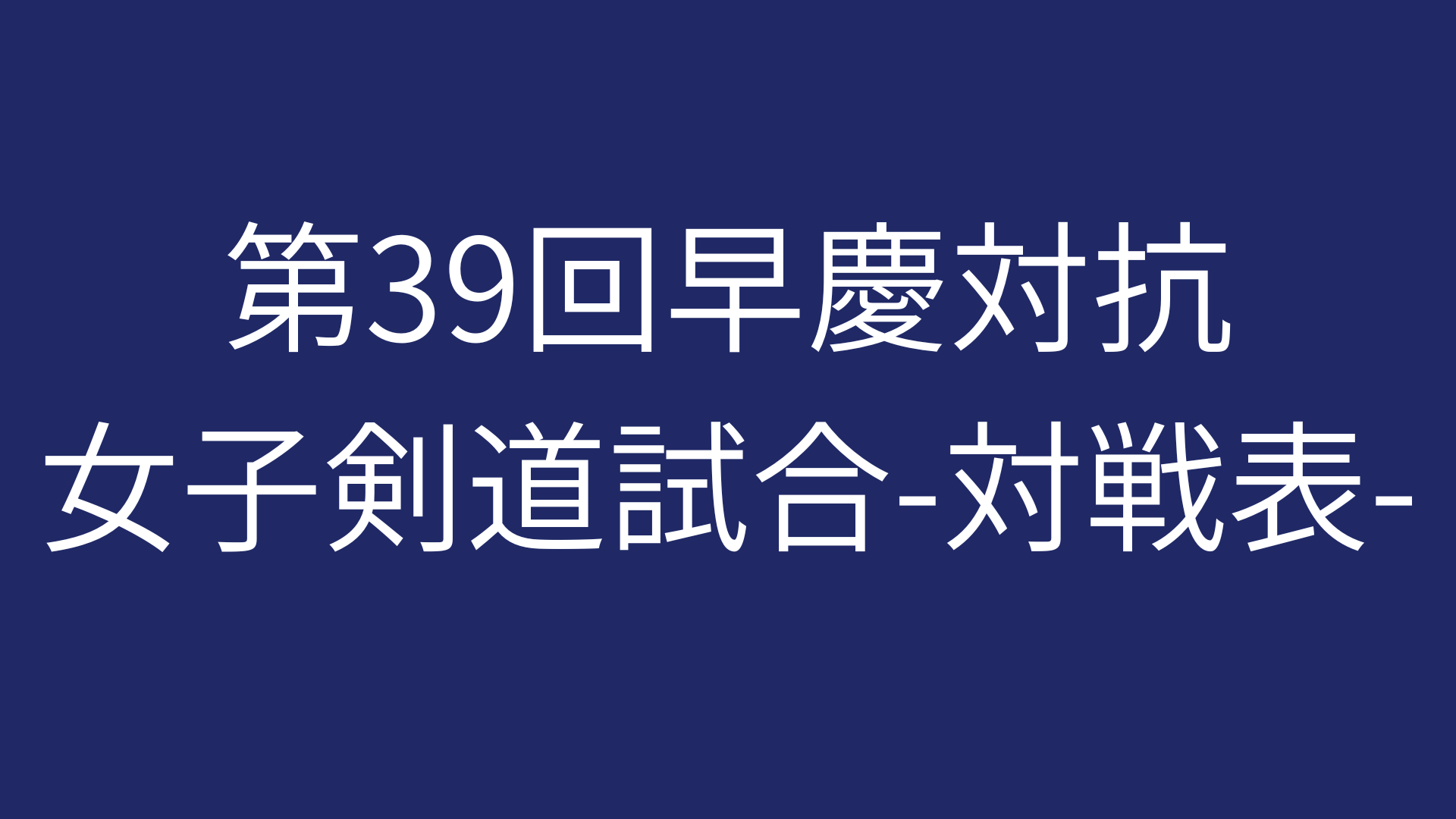八月。道場対抗戦の当日、久しぶりの緊張を味わっていた。インターハイの準決勝よりも、初めてひとりで取引先に行った時よりも、よほど緊張している自覚があった。
「固いよ浦辺選手。もっとリラックス、リラックス」
左隣に座る中倉は、肩を強く叩いてきた。
「そろそろ面つけますか」
逆側の湊に声をかけられ、面を被った。先鋒と次鋒は、試合前に面を装着していなければならない。面紐を締めて立ち上がると、鳥肌が立つような緊張感が襲ってきた。前の試合が終わると同時に、鈴木が手を叩いて立ち上がった。
「よし、いこう」
コート横のスペースを一瞥した。子どもたちと保護者が垂れ幕をもって応援している。垂れ幕には五人の名前が書かれていた。先鋒ダイゴ先生。次鋒ウラベ先生。中堅ナカクラ先生。副将スズキ先生。大将モリタ先生。子どもたちに無様な試合は見せられない。気を引き締め、コートに足を踏み入れた。
先鋒戦、湊の相手も実業団選手だった。試合前に湊が「結構強い選手だけど、まあ大丈夫でしょ」と言っていた。「ほんとか?」と訊くと、湊は不敵に笑った。
「正剣が一番強いんだよ」
湊は言葉通り、開始早々に相面を奪って「大丈夫」なところを見せつけた。立て続けに得意技の引き面。これまで湊と稽古していて、一度も引き技をとったことがない。それほど湊は鍔迫り合いでの駆け引きと、引き技の巧みさに長けていた。
先鋒と次鋒が入れ替わる瞬間、湊は耳元でささやいた。
「頼むよ」
相手は大学生くらいの年齢に見えた。剣道は綺麗ではないが、体力がある。最初は上段に構えてじっくり攻めようとした。しかし相手は意に介さず、性急に打ってくる。ぴょんぴょんと跳びはねる相手にペースを乱され、つい不用意な面を打ってしまった。相手は余裕をもって竹刀を払い、面に真っすぐ打ち込んできた。
「面あり」
応援団から大きな溜め息が漏れた。子どもの反応はわかりやすい。
そのまま見せ場なく、試合を終えた。入れ替わる時、中倉に逆に励まされた。
「大丈夫だよ。俺が取り返す」
その言葉とは裏腹に、中倉は苦戦を強いられた。相手は五段の試合巧者で、中倉が我慢できずに打ったところをうまく応じた。結局、中倉は返し胴と出小手をとられて、二本負けを喫した。うなだれながら引き返す中倉の胴を、鈴木は力強く叩いた。その仕草は、俺に任せろ、と言いたげに見えた。
引き揚げてきた中倉は、面をとると、自分の膝を両拳で強く叩いた。中倉の「くそっ、くそっ」というつぶやきが聞こえた。横顔を盗み見ると、歯を食いしばっている。エリート会社員とは思えない悔しがりようだった。
鈴木の相手は手強かった。竹刀が正中線からまったく動かない。試合中、湊が肩を叩いてきた。
「どっかで見たことあると思ったら、警視庁の機動隊員だ。学生の時に稽古したことある」
機動隊員は鈴木に強烈な突きを見舞った。応援団から悲鳴が上がる。鈴木が敗れれば、その時点でチームの敗北が決定してしまう。機動隊員は突きが決まったと確信したらしく、ふっと剣先を下げた。しかし、旗は一本しか上がらなかった。
その隙を逃さず、鈴木が面に跳んだ。慌てて相手は防御したが間に合わず、鈴木の竹刀が相手の面を捕らえた。応援団から女性の嬌声が上がった。保護者の誰かが叫んだのだろう。鈴木は子どもだけでなく、母親たちからも人気がある。鈴木は相手の反撃を防ぎきり、その一本を死守した。湊がつぶやいた。
「これでノーサイドだな」
ここまでで勝者数、取得本数、ともに五分だった。大将戦で勝った方のチームが勝利する。鈴木は入れ替わる時、森田の耳元で何事か告げた。森田は重厚に頷き、コートに歩を進める。
「今、何て言ったんですか?」
訊くと、鈴木は平然と答えた。
「相手は七段ですよ、って」
「ほんとですか」
「さあ?」
鈴木のささやきが効いたのか、森田は序盤から試合を優位に進めた。森田の動きは五十代とは思えない。踏み込みは強く、振りかぶりは速い。少し我流なところが目立つが、湊が勝負強い、と言った理由もわかる気がする。
試合中盤、相手の大将が面に跳んだところに、森田の返し胴が決まった。応援団がこれまでにないほど湧き上がった。
「森田先生、あと少し!」
「粘れ粘れ!」
応援団が盛り上がると同時に、相手の打突が見る間に鋭さを増した。一本とられる前とは別人のように、的確な打突を繰り出してくる。一分もしないうちに、森田は面を取り返された。相手は勢いに乗ったらしく、更に追加で森田から面を奪った。あまりにもあっけなく、試合は終わってしまった。
五人がコートから離れた後、湊は応援団からパンフレットを受け取り、相手チームのメンバー表を確認した。
「やっぱり相手の大将、七段じゃないじゃん。見てよこれ」
湊はパンフレットを開いて見せる。「範士八段」という文字列が視界に飛びこんできた。
試合後は、再び居酒屋で反省会と称した飲み会がはじまった。一部の女性保護者も来たそうにしていたが、子どもの世話があるということで、渋々帰っていった。鈴木と酒を飲みたい、という魂胆がありありと見えた。
「やっぱり森田さん凄いなあ。範士八段を本気にさせちゃうんだから」
「いや、そんなことありませんわ」
そう言いつつ、森田は湊の賞賛に上機嫌だった。大会には孫も応援に来ており、試合後に「じいちゃんかっこいい」というお誉めの言葉を頂戴したらしいと、湊から聞いていた。対照的に中倉は不満げに言い訳をしている。
「あの会場の床、すごい滑ったんだよね。いつもの体育館ってもっと滑らないでしょ。だから何か、調子が狂っちゃったんだよなあ」
「次頑張りましょ、次」
鈴木が瓶を傾け、中倉のコップにビールを注いだ。そのまま他のコップにも瓶の先を向ける。
「浦辺さんもお疲れさまです」
「いや、とんでもないです。俺のせいで試合負けちゃいましたし」
その言葉に反応して、中倉が振り向いた。
「そんなこと言ったら、私の立場がないでしょう」
「いや、そういうつもりでは……」
「せめて私が一本負けなら、森田さんが勝負に出る必要もなかったのに」
中倉は試合直後と同じように、拳で膝を叩いた。事業部長がこんなに悔しがる姿を会社の部下たちは知らないかもしれない。そのことがなぜか嬉しかった。
「五人で出場できただけでええんですわ」
「今まではひとり分、無条件で二本負けでしたから」
森田の漏らした一言に呼応するように、湊が言った。鈴木は場を総括するように、高らかに宣言した。
「今日の悔しさは、明日の勝利の源です。次回も頑張りましょう!」
どうも鈴木という人はクサいところがあるな。そう思いつつ、そのわざとらしさが心地よかった。会社ではこんなに堂々とクサい台詞を言える人はいない。
「大吾さ、今日もしかしてお父さん来てた?」
「あ、ばれてましたか」
中倉の質問に、湊は照れ臭そうに答えた。
「実は父親が俺の試合の応援に来るの、初めてだったんですよ。死ぬ前に一度はお前の試合を見とくか、とか言って、札幌からわざわざ来てくれたんです」
「泣かせる話ですわ」
森田は涙を拭う真似をした。
鈴木が店員からビールのお代わりを受け取ると、大きな声で宣言した。
「では、我々と大吾のお父さんの今後を祝して、乾杯!」
その日は三次会まで飲み続けた。中倉の「もうすぐ終電だ」という一言で全員が立ち上がり、道場での再会を約束して解散した。
混雑した最終電車の中で、心地よい疲労に包まれていた。窓の外にある家々の明かりが、尾をひいて流れていく。今度広島に帰った時は、道場に顔を出してみるか。最寄り駅のホームに降り立った時、そう決めた。
八月最後の土曜日。
朝からいつものように竹刀と防具をもって体育館に向かうと、玄関から道着袴の湊が飛び出してきた。初めてここに来た時と同じような展開だな、と苦笑していると、湊もにやにやと笑っていた。
「今日はサプライズがあるんだよ」
「サプライズ?」
「まあ来てよ」
湊に続いて、体育館の中へ足を踏み入れた。まだ早い時間ということもあって、子どもや保護者は誰も来ていない。ただ、姿見の前には素振りをしている人影があった。男のようだが、鈴木や中倉、森田とは違うようだった。素振りの速さと鋭さは、その三人とは比べ物にならない。
傍らには竹刀袋が立てかけてあった。もしやと思ってそこに刺繍されている言葉を読みとった。達筆な文字で「妙法学園」と縫われている。もう湊の姿は視界に入っていなかった。
十年前の夏に戻っていた。インターハイ剣道男子個人、最終日の準決勝。片手突きを決めた彼は、試合後にこう言った。「今度、一緒に稽古しようや」
その約束は、今日ようやく実現するらしい。随分長く待たせたものだ。
男は竹刀を振る手を止め、振り返った。もう高校の時のような五厘刈りではない。彼はこちらに近づいてきた。担いでいた竹刀と防具を置き、彼に歩み寄る。
「十年ぶりだな」
石坂の言葉に、思わず微笑んだ。
(了)







 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 武扇
武扇
 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ


 お得セット
お得セット
 防具セット
防具セット
 面
面
 小手
小手
 胴
胴
 垂
垂
 道着
道着
 袴
袴
 竹刀
竹刀
 木刀
木刀
 防具袋
防具袋
 竹刀袋
竹刀袋
 小物
小物
 ギフト
ギフト
 書籍・DVD
書籍・DVD
 クリーニング
クリーニング
 防具修理
防具修理
 剣道面マスク
剣道面マスク
 アウトレット
アウトレット
 居合道
居合道
 日本刀・美術刀剣
日本刀・美術刀剣
 ミツボシ
ミツボシ
 東山堂
東山堂
 松勘
松勘
 日本剣道具製作所
日本剣道具製作所
 西日本武道具
西日本武道具
 栄光武道具
栄光武道具
 信武
信武
 タイヨー産業
タイヨー産業
 武扇
武扇
 博多屋
博多屋
 松興堂
松興堂
 旗イトウ
旗イトウ
 インタビュー お役立ち記事
インタビュー お役立ち記事
 サイズ計測ガイド
サイズ計測ガイド
 GLOBAL SHIPPING GUIDANCE
GLOBAL SHIPPING GUIDANCE